◎『わが星』、ことばと音によるノスタルジア
片山幹生
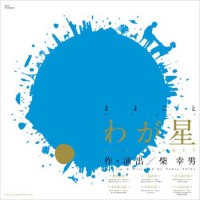 作品の概要
作品の概要
柴幸男作・演出の『わが星』は作者が主宰するままごとによる第一回上演作品として2009年10月に今回の東京公演と同じ三鷹市芸術文化センター星のホールで上演され、好評を博した。作品はこの初演のあと、2010年2月に第54回岸田戯曲賞を受賞している。
『わが星』というタイトルから明らかであるように、この作品はソーントン・ワイルダーの『わが町』に触発されて生まれた作品であり、平凡な日常のかけがえのなさを「死」を対比させることで浮かび上がらせるという点に両作品の共通点がある。作品の世界観には『わが町』の影響は明瞭ではあるが、ラップ・ミュージックとダンスとことばを融合させた複合的な表現を用いて宇宙の100億年の歩みを団地に住むある女の子の生涯に重ねて描き出すという構図によって『わが星』はきわめて独創的で斬新な劇世界を作り出している。
話の中心となるのは「ちーちゃん」と呼ばれる団地に住む一少女である(この役柄を演じた端田新菜のみずみずしさはこの平凡な一少女の寓意性を見事に具現していた)。彼女は父母、姉、祖母の三世代五人家族の次女であり、月ちゃんという同い年の友人がいる。『わが星』ではちーちゃんの誕生から死までが描かれる。このちーちゃんは「地球」の擬人化でもある。そしてこの地球の姿ははるか一万光年かなたにある別の星の少年によって観察されている。彼が見ているのは一万年前の地球の姿であり、彼が見ている時点ではもう消滅しているかもしれない地球の姿ということになる。ちーちゃんの誕生から死の100年は、地球46億年の歴史、そして宇宙100億年の歴史に重なり合う。芝居は「無」の状態からはじまり、80分(上演時間)、100年、100億年の時を同時に表象して、最後に「無」へ回帰して終わる。
「客席は宇宙で、夜空の星を見るようにこの舞台を見る」(『わが星』脚本の冒頭にあるト書き)。会場に入るとなかは薄暗い。客席は壁際に円形状に設置されている。演技は主に中央にある円形の空間の内側およびその周囲で行われる。
音楽劇としての特性:複合的表現がもたらす効果について
『わが星』の上演中には常に時報を知らせるパルスが流れている。劇は時報の規則的なリズムとともに進行する。『わが星』の制作とほぼ同時進行で作曲されたという□□□(クチロロ)の楽曲「00:00:00」は『わが星』の劇作法の基調をなしている。この曲にはいくつかの異なる長さのバージョンが存在するらしいが、『わが星』は「00:00:00」の究極の発展形であるように私には思われる。『わが星』は80分間の一編の長大な演劇的楽曲であり、現代における音楽劇の新たな可能性が十全に示されている。


ラップ音楽を基調とする作品の表現技法は、作品の表現内容とみごとに結び付き、そのメッセージを効果的に増幅させていた。持続的な時報音は時間の不可逆性を強く意識させる。この作品の大きな主題のひとつはわれわれ全てにとって不可避である死、破滅である。人は必ず死ぬし、天体もいずれは終末を迎える運命にある。ひたすら時を刻み続けるパルスはわれわれと地球、宇宙の市と消滅、そしてそれらを包括して表現するこの劇自体の終わりを暗示し続ける。 少しずつ変化を加えながら反復される音楽のフレーズは、時間の円環的動きと結びつく。時間は直線的に進んで行く一方で、春夏秋冬、一ヶ月、一週間、一日といった周期的な流れ方もする。微妙に少しずつずれながら反復される台詞や場面は、音楽とともに、時間の周期的な動きを表象している。らせんを描きながら徐々に前に進んで行く時間のイメージが、音楽、動き、ことばの三者の連動によって鮮やかに表現されている。
台詞のテキスト自体、非常に音楽的に書かれている。対話部分の台詞はほとんどの場合、一行以内に収まる短いものだ。短い台詞がラップのリズムにのってリズミカルにつながる。短い台詞の連なりによって、水面に広がる波紋のようにことばが喚起するイメージが重なり合い、美しい抒情的風景を描き出す。台詞が名詞一語だけの箇所も多い。一語ずつことばが連なっていく。同音の重ね合わせ、意味の連想などによって名詞が羅列されることによって、イメージが大胆に飛躍していく。こうしたことばの操作と音楽の相乗効果を利用して、劇内の世界はあたかも望遠鏡の倍率を急速に変更したかのようにミクロとマクロの間を自在に行き来する。この移動時の感覚は強烈だ。
「わが星」ではラップで歌われる箇所があるが、台詞と歌の部分の境界は曖昧で、その移行は極めて滑らかで自然に行われる。ごく控え目な音の仕掛けが施されることで、ことばが潜在的に持っている音楽性が精妙に引き出され、台詞は心地よい歌となる。ラップで歌われる台詞の多くは日常的なことばの断片で構成されたノスタルジックな叙情詩となっている。白神ももこ振付による群舞がその叙情性にさらなる彩りを加える。いくつかのラップの場面のなかで、私がもっとも印象深かったのは最後のほうにある父と母のデュオの場面だ。円の周囲を回りながら、二人は日常のルーチンをラップにのせて歌う。□□□の美しいメロディのなかでことばを反復させることで、聞き手をありふれた日常の平穏の描写が生み出した甘美な詩情のなかで陶酔させてしまう。
『わが星』は、音楽自体の旋律とリズム、そしてことばに内在する音楽性を巧妙に利用してわれわれの感覚に訴えかける。これらの音楽的な刺激がもたらす快感はわれわれの感情を激しく揺さぶる。 この卓越した音楽的技法ゆえに『わが星』で表明されているあまりに素朴な日常性賛美の世界にわれわれは共感し、受け入れてしまうのだ。
明朗さへの違和感、宗教劇としての『わが星』
音楽という感覚的手段への多大な依拠、作品に漂う健全で素朴なノスタルジーは、この作品を全的に受け入れることを躊躇させる要素でもある。『わが星』は岸田賞を受賞し、多くの観客に支持された作品ではあるが、この作品に対する否定的な声も少なくはない。
私が目にした『わが星』に対する違和感の表明のなかで印象に残っているのは、『ユリイカ』2010年9月号に掲載された内野儀氏の論評である(内野儀「10年代の上演系芸術:ヨーロッパの「田舎」をやめることについて」、『ユリイカ』第42巻10号(2010年9月)、131-139頁)。内野氏は「[日常に対する]いっさいの躊躇やアイロニーなしの絶対的肯定性」を『わが星』の特性とし、作品に見られる「セカイ系」的価値観および「底が抜けたような絶対的『明るさ』」に対する違和感を表明している。
確かに『わが星』には目がくらませるような圧倒的な明るさがある。その日常性の賛美はあまりに無邪気に感じられることもあり、ある種の新宗教に対して抱くような警戒心を持った観客も少なくないはずだ。実は私自身、初演を見たときには『わが星』をそれほど高く評価できなかった。初演時にはむしろ周囲の絶賛のなかで、作品を受け入れることのできない自分に戸惑いを感じていた。
『わが星』の素朴な表現の数々はその素朴さゆえに作品にある種の聖性を付与している。とりわけことばの音楽的反復は、そのことばの連鎖が生み出すノスタルジックなイメージや極小と極大の世界を対比させることで生まれるダイナミックな移動の感覚と結びつくことで、ちょうど読経したり、聖歌を歌っているときに感じるような宗教的な法悦感を生み出してはいないだろうか?『わが星』には観客をマインド・コントロールしかねない巧妙な仕掛けが含まれている(もっともあらゆる演劇作品は多かれ少なかれこうした仕掛けを持っているのだが)。テキストの内容も宗教的な主題とつながりを持っている。「終末」と「死」についての言及、壮大な時空を日常というミクロコスモスを通してのぞき見る語り口、そして光の象徴に、私は地獄、煉獄を経て地球をはなれ天空のかなたの天国を目指すダンテの『神曲 天国篇』の世界観を想起した。『わが星」は死の間際に脳裏に浮かぶという、時間の蓄積を経て磨かれた過去の記憶の点景のシークエンスのようにも思える。エピソードの自由でなめらかな連鎖のなかで並置される日常生活の習慣的な行為が、音楽と身体と声を介して劇詩として昇華されていく瞬間は感動的である。
こうした「宗教的」歌劇としての特性も持つ『わが星』における日常性の賛美は、いわゆる「セカイ系」作品で見られるように、作り手の分身である「私」の周囲にある社会と歴史に対する視線を全く欠いた内閉的な現実逃避に過ぎないものであると受け取られる危険性を内包している。私が初演時に『わが星』を見たときに作品に対して違和感を覚えたのは、作品が提示するノスタルジックなユートピアに何らかのいかがわしさを感じ、警戒心を持ったからかも知れない。
『わが星』の逆説
しかしこの四月の再演時に『わが星』を見たときには、正直に告白すると、私はこの作品の魅力に完全降伏してしまったのだ。再演時に私が『わが星』の世界を初演時のときよりも肯定的に受けとめることができるようになったのにはいくつかの理由があるだろう。一つには作品を再見したり、再見するまでに『わが星』に対する感想、批評を読んだことで、私自身が作品をより深く見ることができるようになったということがあるだろう。
『わが星』のまばゆいばかりの日常性の賛美のむこう側に現実への乾いた諦念がある。見方によってはあの徹底した明朗さには、「どうせ最後は死んでしまう」といった軽やかであるが根強いニヒリズムがあるようにも感じられる。『わが星』柴幸男は心地よい夢心地の楽園を見せながら、常に死を暗示している。あの底抜けのまばゆさは、相反する闇の存在を意識させずにはいられないものでもある。あの甘美なノスタルジーに満ちた幸せな世界はすべて過去の出来事であり、確実な終末が訪れることが作品のなかで冷徹に繰り返し予告されている、という悲観的な物語を『わが星』のなかに読み取ることも可能だろう。 しかし実際には私は他の多くの観客同様、このようなひねくれた悲観主義で『わが星』の再演に立ち会ったわけではなかった。自分でも意外なほど素直に音楽に身を委ね、作品の壮大さに酔い、ノスタルジーに浸り、涙を流した。
自分がなぜ再演時には『わが星』のファンタジーを素直に受け入れることできたのかについて考えてみた。ふと思い当たったのは3月11日に起こった東北大震災である。震災は生々しい残酷さでもってわれわれの日常生活の平穏がいかに脆く、壊れやすいものであることを思い出させた。『わが星』で表象されている理想化された平凡を見たとき、私はその日常の平穏を支えている世界の不安定さを思い描かずにはいられなかった。震災後の日本で私がかかえる漠然とした不安感が、『わが星』の楽園を受け入れやすくする心理状態を作った可能性は大きいように思う。『わが星』が提示する抒情的な美に満ちた日常は、とりわけ震災の後遺症に苦しむ人たちにとって大きな慰安と希望を与えるのではないだろうか。6月に予定されていた福島県いわき市での『わが星』の公演が会場の都合で延期(中止?)されたことを本当に残念に思う。
(初出:マガジン・ワンダーランド第240号、2011年5月11日発行。無料購読は登録ページから)
【筆者略歴】
片山幹生(かたやま・みきお)
1967年生まれ。兵庫県出身。早稲田大学ほかで非常勤講師。専門はフランス文学で、研究分野は中世フランスの演劇および叙情詩。ブログ「楽観的に絶望する」で演劇・映画等のレビューを公開している。
【上演記録】
ままごと『わが星』
【東京公演】三鷹市芸術文化センター星のホール(2011年4月15日-5月1日)
【三重公演】三重県文化会館 中ホール 特設舞台(5月7日-8日)
【名古屋公演】千草文化小劇場(5月12日-13日)
【北九州公演】北九州芸術劇場 小劇場(5月19日-22日)
【伊丹公演】AI-HALL(5月27日-29日)
作・演出・演奏:柴幸男
出演
青木宏幸、大柿友哉(害獣芝居)、黒岩三佳(あひるなんちゃら)、斎藤淳子(中野成樹+フランケンズ)、永井秀樹(青年団)、中島佳子、端田新菜(青年団)、三浦俊輔
スタッフ
音楽:三浦康嗣(口口口)
振付:白神ももこ(モモンガ・コンプレックス)
ドラマトゥルク:野村政之
舞台監督:佐藤恵
演出部:山下翼
演出助手:白川のぞみ(てとあし)
美術:青木拓也
照明:伊藤泰行
照明補佐:富山貴之、南香織
音響:星野大輔
音響補佐:高橋真衣、池田野歩
衣裳:藤谷香子(快快)
写真撮影:青木司
宣伝美術:セキコウ
WEB:CINRA INC,
WEB&Twitter管理:廣野未樹(Unit woi)
制作:ZuQnZ[坂本もも、高橋ゆうこ、林香菜]、森川健太(三鷹市芸術文化振興財団)
制作統括:森元隆樹(三鷹市芸術文化振興財団)
製作総指揮:宮永琢生
特別協力:急な坂スタジオ
協力:こまばアゴラ劇場、舞台美術研究工房 六尺堂、ダックスープ、ロロ、マームとジプシー、LLC10℃、commmons、シバイエンジン
助成:芸術文化振興基金、セゾン文化財団
企画制作:ままごと、ZuQnZ
主催:三鷹市芸術文化振興財団、ままごと
チケット料金:【前売】一般3000円/財団友の会会員2700円【当日】一般3500円/財団友の会会員3150円【高校生以下】前売・当日1000円
助成=公益財団法人セゾン文化財団
「ままごと「わが星」」への6件のフィードバック