◎シアトリカル・プラネタリウムはいかに演劇を拡張するか
柳沢望
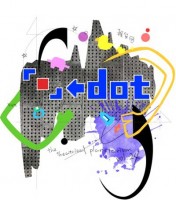 長野市立博物館のプラネタリウムでおこなわれた雑貨団の公演を見に行った。タイトルは「.」(ドット)という。
長野市立博物館のプラネタリウムでおこなわれた雑貨団の公演を見に行った。タイトルは「.」(ドット)という。
雑貨団のことを知ったのは、最近たまたまプラネタリウムでの仕事を始めたからなのだが、長野市立博物館は、雑貨団がプラネタリウムを活用する演劇公演を始めた場所だったそうだ。活動の原点となる場所で、新作の初演がどのように披露されるのか、興味を抱きつつ出かけた。
雑貨団は、プラネタリウムを上演会場にする演劇をつくり続けてもう16年になるという。基本的に演劇上演向きではないプラネタリウムのドームを演劇空間として活用する方法が、手法としてしっかり確立されていることが伺えた。
プラネタリウムは、それ自体ドームシアターの一種であり、劇的な表象の場のひとつだ。今回の公演の中身を取り上げながら、表象の場が持っている社会的な可能性を演劇的な営みがどのように広げられるのかについて、少し考えてみたい。
プラネタリウムを演劇的に活用する雑貨団の手法は、星や宇宙というテーマに潜んでいるドラマを引き出すという内容的な側面と、ドームの特徴を生かした空間構成的な側面に分けて考えてみることができる。
ドーム空間の条件と、天文や宇宙開発にちなんだテーマとを、プラネタリウムという場所が宿してきた場所の力によって生かすこと。プラネタリウムによって演劇上演の効果を高めると同時に、プラネタリウムという場所そのものがもっているドラマを喚起する潜在力を引き出すこと。そこに雑貨団が標榜する「シアトリカル・プラネタリウム」の本領がある。
今回の上演では、宇宙開発の歴史とその未来像を描くことが、宇宙という視野から人間を考え直すというテーマにつながっていて、空間構成的には、(1)借景としてドームへの星空投影を使う。(2)ドームをスクリーンとして、映像を投影する。―という二つの面に整理できる。雑貨団の作品が成功するのは、主題と空間構成がうまくかみ合い、ドーム空間が演劇的な場として成立したときだと言えるだろう。
さて、今回の公演タイトル「.」(ドット)は、コンピューター言語で使われる文字列の「.」と、遠くに見える星が点のように見えるということを掛け合わせたもの。火星まで人類が進出し、宇宙への観光が当たり前になった近未来を舞台に、サスペンス仕立ての物語がコメディータッチで進む。
アニメなどのサブカルチャーにまつわるパロディが満載なあたりの手つきや、小ネタをテンポよく繰り出しつつ入り組んで飛躍のある話が進むという作劇法などは、80年代小劇場を思わせるものだ。そう聞くと今どきの観客は敬遠するかもしれないが、往年の小劇場風スタイルだからといって「遅れている」などと考えなくても良いだろう。問題は、そのスタイルがどのように活用されているか、である。

舞台が始まるのは、大企業に脅かされているような弱小の宇宙観光会社で、新人社員が月観光の新企画をプレゼンする場面からだ。そこから、利権関係が錯綜する月開発をめぐってしのぎを削る大手企業の様子が、チンピラまがいのキャラクター達を配したコメディタッチで描かれる。
そんな争いに宇宙開発を監督する行政サイドも絡むという入り組んだ状況を描きつつ、地球や月、火星まで、広い範囲でコンピューターの不調を起こしてゆく「.」の謎を解く鍵が、宇宙開発に関わるある機関の研究にあるらしいと明らかになるあたりで、錯綜した物語は、火星の近くにあるという謎の信号発信源、その争奪戦に収斂してゆく。
あるときは地上、あるときは月と、めまぐるしく転換する場面は、ドームに投影される映像を「携帯メディアによるテレビ電話的な通話画面」に見立てた、ドームの下での映像と演技の掛け合いという演出を交えて進み、プラネタリウムが描く星空を月の基地にある透明なドームから見た宇宙になぞらえるといった演出も巧妙に組み合わされて、ドームが感じさせる宇宙の広がりは、あたかも舞台がそのまま宇宙空間に漂っているような感覚につながるよう、周到に構成されている。非常に巧みなドーム空間の「借景」だと言えるだろう。
* *
さて、「.」の物語では、エストラゴンとウラディーミルという二機の探査機が重要な役割を演じる。人工知能を搭載し、宇宙空間を旅するふたつの探査機が、お互いに会話し続け、そんな対話から膨らんだ問答が、やがて、人類全体への問いかけに至るというのが、物語全体を枠付ける大きなプロットになっている。
もちろん、これは『ゴドーを待ちながら』を踏まえた名前だ。『ゴドーを待ちながら』の引用は、ゴドーを神とみなす解釈を下敷きにしたもので、参照の仕方としてはベケット作品のキリスト教的な背景を陳腐化してしまったようなところもあったが、それはともかく、『ゴドー』の二人がまさしく人類を代表していたように、「.」のエストラゴンとウラディーミルは、人類にとって宇宙を意識することにどんな意味があるのかといった本質的な問いを担ったキャラクターとして登場する。
コンピューターの誤動作が引き起こす人類存亡の危機と、高度な情報処理による人格シミュレーションの可能性が重なり合い、人格そのものの存在意義、ひいては人類の存在する意味への問いが、この二機の探査機をめぐる活劇と重なり合う。そんな風にいささか入り組んだ筋立てで舞台は進むのだが、その詳細はこれから作品を見る人のために伏せておこう。
ここでは、その問題がからまりあう状況が、あるナンセンスな仕掛けによってあっけらかんと解消されてしまうとだけ述べておこう。そこで、喜劇的な展開によってこそ示すことができる一種のヒューマニズムを衒い無くはっきり描いてみせる作劇は鮮やかで、そこに至る仕掛けが、脚本の構成においても、セノグラフィー的な空間構成においても、見事にかみ合っていたからこそ、クライマックスでの女優(やしろのりこ)の演技は輝きを放つことができたのだろう。
そして、そんなナンセンスが示すのは、人間の未来は常に予想外の可能性に開かれているというシンプルな楽観的ビジョンだ。

宇宙の果てまで旅を続ける探査機のイメージと、どこか調子が崩れた人間たちのコミカルさを対比する締めくくりがおかれるのは、星々の投影効果によって宇宙の果てしない広がりをイメージさせるプラネタリウムのドームである。
広大さをイメージさせる空間の中でのズッコケというのは、それはそれで、ちぐはぐであるからこそ人間は捨てたもんじゃない、と思わせるようなものになっていて、それ自体、発想として珍しくないにせよ、その、あまり感傷まみれではない、むしろ乾いたユーモアは、まるで人類まるごとにむけた軽快な挨拶のようだった。
上演の全体としては、ところどころギャグがかみ合わない場面があったりもしたが、クライマックスがもたらしたカタルシスは紛れも無い演劇的達成だったと言える。
さて、『ゴドー』が、結末を欠いた悲劇的なプロットの宙吊りを、喜劇的で無為なネタの消尽によって埋めるような作品だったとすれば、雑貨団の「.」は、人間の存在する意味をめぐる大きな問いをナンセンスなギャグで脱臼させるというしかたで、その問いに正面から回答するものになっている。
ベケットが本質的な問いを喜劇的精神をもって扱っていたとするなら、雑貨団は雑貨団で、本質的な問いに喜劇的な回答を与えようとしている。ベケットの透徹した劇作が掘り下げた喜劇と悲劇の相克に比べたら、雑貨団はその徹底においてはるかに及ばないのだとしても、この上演で行われたパロディー的な『ゴドー』への参照は、ささやかではあれ、日本的なベケット受容の文脈を踏まえた上での、単なる名作への寄りかかりに終わらない、ベケットへのひとつの応答になりえていただろう。宇宙空間では、朝日が昇りも沈みもしないが、一度投げられたものはどこまでも進むのだ。
* *
ところで、フランセス・イエイツは『世界劇場』において、グローブ座の舞台構成がいかにコスモロジカルな意味合いを帯びたものだったかを語っていたわけだが、現代の劇場は、どんな作品でも無差別に上演できるよう舞台空間を意味を欠いた等質空間に還元するところで、むしろある種の脱コスモロジーを象徴するような場所だ。脱コスモロジーという面では、プロセニアム型の舞台も、アリーナ型の舞台も、さほどの違いはないだろう。
『ゴドー』では、「舞台」に関する自己言及的な楽屋オチが、それ自体では脱コスモロジー的な劇場にヨーロッパ文化史をその神話的な基層からまるごと招来していたとすれば、「.」でドームに持ち込まれたナンセンスは、人類史をまるごとドームに招来するようなものであり、それはドーム空間のなかで現代的なコスモロジーを模索し、ドームという形象に未来のコスモロジーを重ね書きするような試みでもあったのだろう。
この上演で、プラネタリウムは、演劇がかつて持っていたコスモロジーを別の仕方で再び手にするための装置として活用されていたようである。
そうした観点から言えば、雑貨団の舞台は、少なくともそれが最良のパフォーマンスを達成したときには、単なるプラネタリウム上映と演劇上演の掛け合わせという試行を超えて、演劇の可能性とプラネタリウムの可能性のそれぞれを本質的なレベルで結びつけるものになりえているだろう。シアトリカル・プラネタリウムというネーミングも伊達ではない。
さて、最後に、科学技術に関するアウトリーチという側面から見た場合の雑貨団の達成について、その演劇的な意義を検討しておこう。その点で雑貨団の取り組みは、平田オリザの「ロボット演劇」と好対照を成していると思われる。
科学と人間という主題やロボット技術的な挑戦という面で「ロボット演劇」の達成は大きいものかもしれないが、それはあくまで演劇の「応用」であり、演劇という技法や劇場という場の「拡張」ではないだろう。
一方、雑貨団が取り上げている事柄は、主題的にはすでによく知られていたり少し考えればわかることをより広く伝えようとしているだけであって、それほど特筆すべき達成とは言えないのかもしれない。おそらく、天文学や宇宙開発に関する主題的な拡張とは言えないだろう。
だが、雑貨団は劇的な変容の力によってプラネタリウムという場所が秘めていた劇的な潜在性を現実化している。そのこと自体、演劇を拡張する試みが成立していることの証だろう。
平田オリザの「ロボット演劇」が、技術をめぐる表象を劇場の既存秩序の中に回収しているとすれば、雑貨団は、演劇という表象の技法によってプラネタリウムという表象の場を再編してみせたのだ。
この雑貨団の取り組みは、単なるコミュニケーション促進のための演劇の応用にとどまらず、劇的な表象の場の変容へとつながっているように思われる。それぞれの場所を変容させるための新たな技法の獲得は、演劇そのものの拡張に他ならないのである。
(8月18日所見)
【筆者略歴】
柳沢望(やなぎさわ・のぞみ)
1972年生まれ長野県飯田市出身。法政大学大学院博士課程(哲学)単位取得退学。現職は飯田市美術博物館学芸係(プラネタリウム担当)。
・ワンダーランド寄稿一覧:http://www.wonderlands.jp/category/ya/yanagisawa-nozomi/
【上演記録】
雑貨団 The Theatrical Planetarium vol.24「.」←dot (2011夏 全国ツアー)
長野市立博物館プラネタリウム(長野県)(2011年8月18日)
入館料:500円
●キャスト(LIVE)
やしろのりこ
オグラミツヒロ
じゃっかる
小林善紹
渡邉亜希子
リベロ(劇団音速かたつむり)
●キャスト(REC=映像のみ出演)
林真紀子
山下りさ
雨宮俊夫
若井誠
●スタッフ
脚本・演出:小林善紹
映像:若井誠
音楽:Tu-g,/滝川耕平
3DCG:宙飛重工(zakkadan project)
衣裳:雑貨団
装置:雑貨団
照明:雑貨団
制作:西池亜希子/山下りさ/柴原崇/林真紀子
プラネタリウム操作:各上演館
>> 公演スケジュール
「雑貨団「.」←dot」への24件のフィードバック