◎「小さな」個人の身体から「大きな」ポテンシャルを探る
武藤大祐(ダンス批評)

ユネスコの下部組織である国際演劇協会・日本センターが隔年で開催してきた、「アジアダンス会議」の三回目が2月に東京で開かれた。アジア各地から集まった振付家、批評家、オーガナイザーなど14人の参加者が一週間に渡ってプレゼンテーションや討論、ワークショップを行いながら、ダンスを通してアジアを、またアジアを通してダンスを、じっくり考えてみたのである。筆者の怠慢でやや遅くなってしまったが、3月末に刊行された記録集の宣伝も兼ねて、二回に分けて報告したいと思う。
 私の記憶の中に私の姿がないのは、言われてみれば至極当然のことである。鏡を見ている時間の記憶は別にしても、写真やビデオでも撮っていなければ、自分自身がいつどこでどのようなことをして、その様子がどんなだったかを見ることができない。たとえ撮っていたとしても、事後的に確認する、私の記憶にとっては傍証のようものでしかない。そして、忘れてしまえばその時間が消滅する。無論、過去にあった時間が消えてなくなるわけではないが、その時間がどのようなものであったか辿れなくなる。初めから見ることができない自分の姿はおろか、自分の耳で聞き取っていたはずの会話もである。そして、忘れたことも忘れてしまえば、それは二度と引き出されることはない。
私の記憶の中に私の姿がないのは、言われてみれば至極当然のことである。鏡を見ている時間の記憶は別にしても、写真やビデオでも撮っていなければ、自分自身がいつどこでどのようなことをして、その様子がどんなだったかを見ることができない。たとえ撮っていたとしても、事後的に確認する、私の記憶にとっては傍証のようものでしかない。そして、忘れてしまえばその時間が消滅する。無論、過去にあった時間が消えてなくなるわけではないが、その時間がどのようなものであったか辿れなくなる。初めから見ることができない自分の姿はおろか、自分の耳で聞き取っていたはずの会話もである。そして、忘れたことも忘れてしまえば、それは二度と引き出されることはない。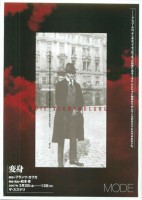 作品がそれのみによって完結されないこととして、たとえばプロセスの重視は、美術ならばプロセスアートやコンセプチュアルアートの一端を占める作品などで知られている。その方法を演劇にあてはめるならば、たとえばリーディングやワーク・イン・プログレスなどを経て、それが公演されるまでの軌跡を公開した作品を指すことになるのだろうか。
作品がそれのみによって完結されないこととして、たとえばプロセスの重視は、美術ならばプロセスアートやコンセプチュアルアートの一端を占める作品などで知られている。その方法を演劇にあてはめるならば、たとえばリーディングやワーク・イン・プログレスなどを経て、それが公演されるまでの軌跡を公開した作品を指すことになるのだろうか。 2007年3月、チュニジアのファミリア・プロダクションが、「東京国際芸術祭」に再登場した。演出家ファーデル・ジャイビと、脚本家で女優のジャリラ・バッカールを核とする、この演劇集団は、メンバーを固定した劇団ではないようだが、前回、2005年に「ジュヌン-狂気」で公演したときと同じ出演者を今回も認めることができた。
2007年3月、チュニジアのファミリア・プロダクションが、「東京国際芸術祭」に再登場した。演出家ファーデル・ジャイビと、脚本家で女優のジャリラ・バッカールを核とする、この演劇集団は、メンバーを固定した劇団ではないようだが、前回、2005年に「ジュヌン-狂気」で公演したときと同じ出演者を今回も認めることができた。 3月末、『関わりを解剖する二つの作品』と題して、手塚夏子の振付作品が2本上演された。手塚夏子は近年『私的解剖実験』と題したシリーズによってダンスの方法論を模索する試みを続けてきたが、今回の二作品では、今まで探求されてきた方法論が組み合わされ、立体的な広がりを見せ始め、手塚の方法論のひとつの到達点を示すと共に、更なる可能性を予感させるものになった。
3月末、『関わりを解剖する二つの作品』と題して、手塚夏子の振付作品が2本上演された。手塚夏子は近年『私的解剖実験』と題したシリーズによってダンスの方法論を模索する試みを続けてきたが、今回の二作品では、今まで探求されてきた方法論が組み合わされ、立体的な広がりを見せ始め、手塚の方法論のひとつの到達点を示すと共に、更なる可能性を予感させるものになった。 この2月に彩の国さいたま芸術劇場でヤン・ファーブルの「わたしは血」を観た。その2カ月足らず後、同じベルギー人という以外何の予備知識もなしに、同じ劇場でヤン・ロワースの「イザベラの部屋」を観た。当然ながら舞台から受けた印象と感動の強度はそれぞれ違うが、どちらもダンス、音楽、演劇、美術が融合した作品だった。
この2月に彩の国さいたま芸術劇場でヤン・ファーブルの「わたしは血」を観た。その2カ月足らず後、同じベルギー人という以外何の予備知識もなしに、同じ劇場でヤン・ロワースの「イザベラの部屋」を観た。当然ながら舞台から受けた印象と感動の強度はそれぞれ違うが、どちらもダンス、音楽、演劇、美術が融合した作品だった。 ムスタヒールアリスの「バグダットの夢」という作品を見た。ムスタヒールアリスはイラクのカンパニー。不安定で、成田に着くまではほんとうに来ることができるかどうかもあやぶまれた状況下から、日本が初演という作品を携えてやってきた。それは、雨が降ると水に浸されてしまう古い家に耐え忍びながら住む家族の話であった。不幸な状況は人間関係の不全と不安を呼び、苛立ちや悲しみが降り止まぬ雨に浸されていく。そこに狂ったひとりの若者がやってきてすべてを破壊してしまう。跡に残ったのは夥しい死と亡骸。暖かな屋根の下に住みたいというささやかな希望さえも終える。
ムスタヒールアリスの「バグダットの夢」という作品を見た。ムスタヒールアリスはイラクのカンパニー。不安定で、成田に着くまではほんとうに来ることができるかどうかもあやぶまれた状況下から、日本が初演という作品を携えてやってきた。それは、雨が降ると水に浸されてしまう古い家に耐え忍びながら住む家族の話であった。不幸な状況は人間関係の不全と不安を呼び、苛立ちや悲しみが降り止まぬ雨に浸されていく。そこに狂ったひとりの若者がやってきてすべてを破壊してしまう。跡に残ったのは夥しい死と亡骸。暖かな屋根の下に住みたいというささやかな希望さえも終える。