◎「どこでもないここ」のリアル
高橋宏幸
 その舞台空間は、見ている観客にいびつな感覚を与える。ただでさえ低く作られている天井は、舞台の奥にいくほどさらに低くなり、柱や窓も斜めになるなど、遠近法の焦点は微妙にずらされている。客席に座り舞台を見ているものにとっては、閉塞感をともなう。だが、客席の天井まで低くしているわけではないので、見つめる視線のみがその空間には囲われる。 白い壁の両面にいくつも開けられた、小さな明り取りの窓から差し込む光も同じように、まるである狭い空間を外側から覗き込むような働きをしている。それは客席から見つめる視線と同じように、舞台空間を取り巻く視線となっている。見るもののまなざしは捕われたような圧迫感を受けるのに、見るものの身体だけは取り残される奇妙な感覚が残る。
その舞台空間は、見ている観客にいびつな感覚を与える。ただでさえ低く作られている天井は、舞台の奥にいくほどさらに低くなり、柱や窓も斜めになるなど、遠近法の焦点は微妙にずらされている。客席に座り舞台を見ているものにとっては、閉塞感をともなう。だが、客席の天井まで低くしているわけではないので、見つめる視線のみがその空間には囲われる。 白い壁の両面にいくつも開けられた、小さな明り取りの窓から差し込む光も同じように、まるである狭い空間を外側から覗き込むような働きをしている。それは客席から見つめる視線と同じように、舞台空間を取り巻く視線となっている。見るもののまなざしは捕われたような圧迫感を受けるのに、見るものの身体だけは取り残される奇妙な感覚が残る。

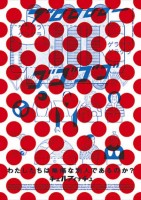
 今年も、年間の最低映画に贈られるゴールデン・ラズベリー賞が決まった。めでたく受賞してくれたのは「トランスフォーマー/リベンジ」であるが、なにより油断できない気にさせるのは、この映画が「当たった」という畏るべき事態である。巨大なレゴ・ブロックのごときロボットたちが、せわしくパーツを組み替えながらめまぐるしく変身してみせる、というか変身してみせるだけのこの映画は、映画を観ているというよりグラフィック・アプリケーションのデモ画面を見せられているような、侘びしくも場違いな気分を我々に味あわせる。にもかかわらず、その退屈を求めて映画館に人は詰めかけたのだ。世の中はまだからくりの手の内がすっかり透けた玩具がお気に入りらしい。2012年など飛んでもない。まだまだ人類は滅べまい。
今年も、年間の最低映画に贈られるゴールデン・ラズベリー賞が決まった。めでたく受賞してくれたのは「トランスフォーマー/リベンジ」であるが、なにより油断できない気にさせるのは、この映画が「当たった」という畏るべき事態である。巨大なレゴ・ブロックのごときロボットたちが、せわしくパーツを組み替えながらめまぐるしく変身してみせる、というか変身してみせるだけのこの映画は、映画を観ているというよりグラフィック・アプリケーションのデモ画面を見せられているような、侘びしくも場違いな気分を我々に味あわせる。にもかかわらず、その退屈を求めて映画館に人は詰めかけたのだ。世の中はまだからくりの手の内がすっかり透けた玩具がお気に入りらしい。2012年など飛んでもない。まだまだ人類は滅べまい。 日暮里シアターアーツ/フェスティバル(2.12-3.21)参加作品の『作品No.7』を観て、再び舞台表現における<言葉と身体>について考えさせられた。再び、というのは5年前にこの集団の作品として初めて観た『ハムレットマシーン』によって、舞台表現の根幹である(と思われる)<言葉と身体>の問題を考えるうえで大いに刺戟を受けたからだ。それはハイナー・ミュラーの「ハムレットマシーン」を上演することの意味と正面から向き合った作品だったが、その中で佐々木敦という若い肥満体の俳優が、金属バットを振り回してテレビやテープデッキ、机を次々に叩き壊すシーンがあった。そのナマの破壊力はすさまじく、客席にいて背筋が寒くなるような怖さを覚えたものだが、同時に、彼の身体から発する負のエネルギーが、経済弱者へと追いやられた現代日本の若者層の鬱屈や怒りとダブって見えた。そして破壊シーンは痛ましくも共感できるものに変わっていた。セリフがない分、それは直接的だった。
日暮里シアターアーツ/フェスティバル(2.12-3.21)参加作品の『作品No.7』を観て、再び舞台表現における<言葉と身体>について考えさせられた。再び、というのは5年前にこの集団の作品として初めて観た『ハムレットマシーン』によって、舞台表現の根幹である(と思われる)<言葉と身体>の問題を考えるうえで大いに刺戟を受けたからだ。それはハイナー・ミュラーの「ハムレットマシーン」を上演することの意味と正面から向き合った作品だったが、その中で佐々木敦という若い肥満体の俳優が、金属バットを振り回してテレビやテープデッキ、机を次々に叩き壊すシーンがあった。そのナマの破壊力はすさまじく、客席にいて背筋が寒くなるような怖さを覚えたものだが、同時に、彼の身体から発する負のエネルギーが、経済弱者へと追いやられた現代日本の若者層の鬱屈や怒りとダブって見えた。そして破壊シーンは痛ましくも共感できるものに変わっていた。セリフがない分、それは直接的だった。 AVにさしたる興味もなく、したがって持田茜の存在も知らず、作・演出のニシオカ・ト・ニールがどのような才能かもわからず、ただ自分のところの次回公演に出演してくれる女優が出ているからという理由だけで観に行った女魂女力 其の壱『しじみちゃん』は本年最初の佳作だった。これを拾い物という。
AVにさしたる興味もなく、したがって持田茜の存在も知らず、作・演出のニシオカ・ト・ニールがどのような才能かもわからず、ただ自分のところの次回公演に出演してくれる女優が出ているからという理由だけで観に行った女魂女力 其の壱『しじみちゃん』は本年最初の佳作だった。これを拾い物という。 ★カトリヒデトシさんのお薦め
★カトリヒデトシさんのお薦め