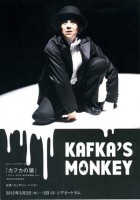◎道化の魔法がひらく 祈りのような情景
鈴木励滋

行進を促すようなリズムをドラムが刻む冒頭、タンスの上によじ登り仁王立ちする女。セピア色に見える景色の中で、女は「ふざけんじゃねぇ、くだらねぇ」と呪詛のような言葉を怒鳴りちらしているのだが、はたして彼女の怒りはどこへ向かっているのだろうか。
この印象的な場面は、589nmの波長以外の色を見えなくしてしまうナトリウムランプの効果だ。東野祥子を始めとして多くのダンサーとも組んできた照明の筆谷亮也の鮮やかな仕事で、次のシーンで明かされる女の肌の秘密を際立たせることに成功した。意表をつきつつも単に奇抜さにとどまらない誠に巧みなオープニングだった。
“子供鉅人「バーニングスキン」” の続きを読む