◎追憶を促すツールとしてのカフカ風変身か
山田ちよ(演劇ライター)
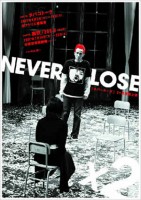 高校3年生の男子4人が登場、恋愛や性体験、就職や遊びなどの話から、この年ごろらしい、大人と子どもの混じり合う心が浮き彫りになる。内面の繊細さを感じさせるが、壊れやすいのでなく、前向きに考えるたくましさや明るさがある。話題があちこちに飛ぶ会話をスムーズに回した4人の演技には、仲間同士のきずなを大切にしようとする内面も表れていた。
高校3年生の男子4人が登場、恋愛や性体験、就職や遊びなどの話から、この年ごろらしい、大人と子どもの混じり合う心が浮き彫りになる。内面の繊細さを感じさせるが、壊れやすいのでなく、前向きに考えるたくましさや明るさがある。話題があちこちに飛ぶ会話をスムーズに回した4人の演技には、仲間同士のきずなを大切にしようとする内面も表れていた。
小劇場レビューマガジン
◎追憶を促すツールとしてのカフカ風変身か
山田ちよ(演劇ライター)
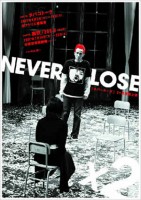 高校3年生の男子4人が登場、恋愛や性体験、就職や遊びなどの話から、この年ごろらしい、大人と子どもの混じり合う心が浮き彫りになる。内面の繊細さを感じさせるが、壊れやすいのでなく、前向きに考えるたくましさや明るさがある。話題があちこちに飛ぶ会話をスムーズに回した4人の演技には、仲間同士のきずなを大切にしようとする内面も表れていた。
高校3年生の男子4人が登場、恋愛や性体験、就職や遊びなどの話から、この年ごろらしい、大人と子どもの混じり合う心が浮き彫りになる。内面の繊細さを感じさせるが、壊れやすいのでなく、前向きに考えるたくましさや明るさがある。話題があちこちに飛ぶ会話をスムーズに回した4人の演技には、仲間同士のきずなを大切にしようとする内面も表れていた。
◎ぶっ飛んだ展開で後味スッキリさわやか
鈴木麻奈美(wonderland執筆メンバー)
 劇団初見。
劇団初見。
タイトルとチラシからどんだけ固い反米の話なんだろうとちょっと思ったけど、全然そんなことはなく、社会派? 難しい話? と、心配するだけ無駄でした。
肩の力を抜いて楽しめる、むしろ肩肘張ってたら楽しめないかもしれない、拍子抜けするほどにポップでキャッチーな作品。
◎想像力への尋常ならざる触手
北嶋孝(マガジン・ワンダーランド)
 子供のころ、桜の季節が過ぎると心底ホッとした。ぼくの生家は幸か不幸か公園に隣接し、いつも花見客のどんちゃん騒ぎに巻き込まれたのだ。深夜まで喧嘩騒ぎが続き、一升瓶で殴られた血だらけの酔客がよく救急車で運ばれた。残された反吐やゴミの山を翌朝かたずけるのがぼくらの仕事になる。桜の季節はうんざりする厄災、憂鬱の季節だった。
子供のころ、桜の季節が過ぎると心底ホッとした。ぼくの生家は幸か不幸か公園に隣接し、いつも花見客のどんちゃん騒ぎに巻き込まれたのだ。深夜まで喧嘩騒ぎが続き、一升瓶で殴られた血だらけの酔客がよく救急車で運ばれた。残された反吐やゴミの山を翌朝かたずけるのがぼくらの仕事になる。桜の季節はうんざりする厄災、憂鬱の季節だった。
もうひとつのグローバル化への幕開け 山関英人(演劇ジャーナリスト) 日中共同プロジェクト公演の『下周村』(新国立劇場制作)は、舞台の受容の仕方に一石、を投じた。それは、国境を越える作品のあり方-普遍性の獲得-の理想 … “日中共同プロジェクト公演 『下周村』” の続きを読む
もうひとつのグローバル化への幕開け
山関英人(演劇ジャーナリスト)
日中共同プロジェクト公演の『下周村』(新国立劇場制作)は、舞台の受容の仕方に一石、を投じた。それは、国境を越える作品のあり方-普遍性の獲得-の理想像を示した、とも云えるだろう。そして、『下周村』はそれを自己言及的に(作品でもって)語ってみせた。
◎思い切ってぶっ飛んだ、演劇常識に挑戦するみごとな爆笑劇
西村博子(アリスフェスティバル・プロデューサー)
 芝居は水ものとはよく聞くことばだが、ほんとにその通りだなあと改めて思った。鈴木厚人作・演出の「父産」を初め見た日、随所で客席に笑いが起こり、終わると熱い拍手が長く続いた。私もいっしょうけんめい拍手。口笛うまく吹けなくてカーテンコールに呼び出せなかったのが残念なほどだった。が、ラクは、周りから時々クスッと忍び笑いが聞こえるぐらい。同じように好感持った大きな拍手で終わったが、思いなしか、笑いを含んだというより、メッセージ受け取りましたといった感じの、マジメ拍手だった。ラクの方がセリフ噛む人もほとんどなく、舞台は遥かに分かりやすくなっていたのに、である。ラクに向ってどんどん盛り上がっていく……はずなのに!? ほんの一呼吸ずつのテンポの遅れか? それとも客席にまでビンビン伝わってきた、あれはあまりに真面目な俳優たちの緊張感のせいだったろうか? その点だけ惜しかった。
芝居は水ものとはよく聞くことばだが、ほんとにその通りだなあと改めて思った。鈴木厚人作・演出の「父産」を初め見た日、随所で客席に笑いが起こり、終わると熱い拍手が長く続いた。私もいっしょうけんめい拍手。口笛うまく吹けなくてカーテンコールに呼び出せなかったのが残念なほどだった。が、ラクは、周りから時々クスッと忍び笑いが聞こえるぐらい。同じように好感持った大きな拍手で終わったが、思いなしか、笑いを含んだというより、メッセージ受け取りましたといった感じの、マジメ拍手だった。ラクの方がセリフ噛む人もほとんどなく、舞台は遥かに分かりやすくなっていたのに、である。ラクに向ってどんどん盛り上がっていく……はずなのに!? ほんの一呼吸ずつのテンポの遅れか? それとも客席にまでビンビン伝わってきた、あれはあまりに真面目な俳優たちの緊張感のせいだったろうか? その点だけ惜しかった。
◎不安定になった体にこそワクワクする
伊藤亜紗(ダンス批評)
 これまで砂連尾理(じゃれお・おさむ)とのコンビ、通称「じゃれみさ」をベースに活動してきた京都在住のダンサー、寺田みさこのソロ公演。余談だがダンスの公演は怒濤のように2-3月に集中しており、逆に年度替わりの4-5月はシーズンオフなので(助成金など公演運営上の都合らしい)、6月に入ってようやく本格的に始動してきたという感じだ。
これまで砂連尾理(じゃれお・おさむ)とのコンビ、通称「じゃれみさ」をベースに活動してきた京都在住のダンサー、寺田みさこのソロ公演。余談だがダンスの公演は怒濤のように2-3月に集中しており、逆に年度替わりの4-5月はシーズンオフなので(助成金など公演運営上の都合らしい)、6月に入ってようやく本格的に始動してきたという感じだ。
◎自意識は果てしなくシッポを追いかける
木俣冬(フリーライター)
 「好き?好き?大好き?」(世界が、演劇が)という問いが頭の中をグルグルと駆けめぐった。
「好き?好き?大好き?」(世界が、演劇が)という問いが頭の中をグルグルと駆けめぐった。
劇場に入ると、横長の舞台を観客が2方向から見る対面式になっている。入り口から見ると下手側に、シェイクスピアの肖像画。中央にごく普通のテーブルと椅子。上手側には布団と棚とCDラジカセがある。上手の入り口はドアはなくノブだけがついている。
◎わたしたちの中に、今ではもう不可能になったあの旅が
村井華代(西洋演劇理論研究)

国家的イデオロギーが個人のセクシュアリティを侵し爆発する。天使は聖処女ではなくエイズを発症したゲイ青年を訪れる。預言の書はキッチンの床下に隠されている。
トニー・クシュナーを一躍20世紀アメリカを代表する劇作家に仕立てた『エンジェルス・イン・アメリカ』(第1部:1991、第2部:1992)。人間の生臭い心身を舞台に、実に様々な次元が交錯する姿が描かれている。ユダヤ人同性愛者という十字架を背負ったクシュナーにとって、個人の憐れな肉体が巨大な国家的・宗教的イデオロギーに蝕まれるというのは、しごく具体的で日常的な自覚であるように思える。
近代的制度の中で平和に生きる「普通の」人間なら気づきもしない警告が聞こえるのは多分不幸なことだ。しかし、だからこそ性的・民族的・国家的マイノリティは現代演劇においては預言者を演じうるのであり、またそうなる運命にあるのだろう。
今春、散歩しながら見る演劇「ポタライブ」の新作2本がアゴラ劇場の「冬のサミット」参加作として上演された。作演出は岸井大輔。舞台となったのはアゴラ劇場がある駒場周辺と、アトリエ春風舎がある小竹向原駅周辺。2つの町からドラ … “#5.ポタライブの『界』/そして『museum』を抜け出て” の続きを読む
今春、散歩しながら見る演劇「ポタライブ」の新作2本がアゴラ劇場の「冬のサミット」参加作として上演された。作演出は岸井大輔。舞台となったのはアゴラ劇場がある駒場周辺と、アトリエ春風舎がある小竹向原駅周辺。2つの町からドラマをすくいあげてみせたこの連続公演は見事な対照をなして、ポタライブの到達点を示し、その更なる可能性をも開いて見せた。(本稿はCutInに寄稿した原稿に加筆訂正したものです。投稿の際、伊東沙保さんの名前を伊藤と間違えていました。お詫びして訂正します。)
◎忘れていた記憶が蘇ってくる面白さ
西村博子(アリスフェスティバル・プロデューサー)
 「ひとりシェークスピアを見てみませんか?」-Kさんからお誘いをいただいたとき、エエッ?? そんなことできるのオ?と驚いた。大体がシェークスピアはもう沢山!の食傷気味。よっぽどでないと動かないぞと思ってる私のこと。おまけに行き先は北千住とか。JRの路線地図を眺めたら、うちから軽く1時間半はかかりそう。もし誘ってくれた人がKさんでなければ、そしてもしも出しものがシェークスピアのいわば処女作、日本じゃ見たことない「ヘンリー六世(第1部)」でなかったら、決して行かなかったにちがいない。
「ひとりシェークスピアを見てみませんか?」-Kさんからお誘いをいただいたとき、エエッ?? そんなことできるのオ?と驚いた。大体がシェークスピアはもう沢山!の食傷気味。よっぽどでないと動かないぞと思ってる私のこと。おまけに行き先は北千住とか。JRの路線地図を眺めたら、うちから軽く1時間半はかかりそう。もし誘ってくれた人がKさんでなければ、そしてもしも出しものがシェークスピアのいわば処女作、日本じゃ見たことない「ヘンリー六世(第1部)」でなかったら、決して行かなかったにちがいない。