◎新しい女性性を巡って(鼎談)
落雅季子+藤原央登 +前田愛実
2011年に大きな話題を集めた芸劇eyes番外編「20年安泰。」。ジエン社、バナナ学園純情乙女組、範宙遊泳、マームとジプシー、ロロの五団体が、20分の作品をショーケース形式で見せる公演でした。それに次いで今年9月に上演されたのが、第二弾「God save the Queen」です。今回の五劇団を率いるのは、同じく若手でも女性ばかり。そのことにも着目しながら、この舞台について三人の方に語っていただきました。(編集部)
“東京芸術劇場「God save the Queen」” の続きを読む
 『わが星』『スイングバイ』と、柴幸男が紡ぎ出した2つの劇世界に触れた私が抱いたのは、この人は壮大なロマンティストなのではないかということである。
『わが星』『スイングバイ』と、柴幸男が紡ぎ出した2つの劇世界に触れた私が抱いたのは、この人は壮大なロマンティストなのではないかということである。 幕開け、素舞台で「清水の舞台から飛び降りた」とテンション高くアクション付きでカットイン。以後およそ50分に渡って鷲津神ヒカルというケバケバしいメイクを施した女子高生の、入学時から2年生の修学旅行までの高校生活の顛末を、速射砲のようにギャグを交えながら話し続ける。終始、冒頭のテンションを崩すことなく、言葉に憑かれたように小気味よいテンポと節回しで駆け抜けた女子高生を演じたのは、柿喰う客という集団の女優、七味まゆ味。大阪は一日だけ公演されたこの一人芝居は、久しぶりに役者体の魅力を余すところなく体感できた舞台であった。
幕開け、素舞台で「清水の舞台から飛び降りた」とテンション高くアクション付きでカットイン。以後およそ50分に渡って鷲津神ヒカルというケバケバしいメイクを施した女子高生の、入学時から2年生の修学旅行までの高校生活の顛末を、速射砲のようにギャグを交えながら話し続ける。終始、冒頭のテンションを崩すことなく、言葉に憑かれたように小気味よいテンポと節回しで駆け抜けた女子高生を演じたのは、柿喰う客という集団の女優、七味まゆ味。大阪は一日だけ公演されたこの一人芝居は、久しぶりに役者体の魅力を余すところなく体感できた舞台であった。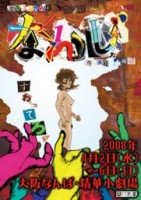 開演前の劇場で流れていた尾崎紀世彦の『また会う日まで』。客入れ音楽のみならず、随所に挿入歌として使用される歌謡曲が未経験のノスタルジーを喚起し、それと共に原色鮮やかな照明と有り余る身体の力をバカバカしい笑いとギャグへ接続して駆け抜けてゆく悪い芝居の劇世界は、そのセンスの良さに反し、演劇を志向する自己と刹那の享楽を求めて観客席に座る我々への冷めた視線によって早くも一つの文体を獲得している。この根底に流れる基本テーゼこそ、この集団が他の若い集団と峻別した意識の高さの発露となっているのだが、舞台を観ながらではなぜ彼らは演劇というジャンルで表現活動をしているのか、なぜ演劇でなければならなかったのかということを考えさせられた。
開演前の劇場で流れていた尾崎紀世彦の『また会う日まで』。客入れ音楽のみならず、随所に挿入歌として使用される歌謡曲が未経験のノスタルジーを喚起し、それと共に原色鮮やかな照明と有り余る身体の力をバカバカしい笑いとギャグへ接続して駆け抜けてゆく悪い芝居の劇世界は、そのセンスの良さに反し、演劇を志向する自己と刹那の享楽を求めて観客席に座る我々への冷めた視線によって早くも一つの文体を獲得している。この根底に流れる基本テーゼこそ、この集団が他の若い集団と峻別した意識の高さの発露となっているのだが、舞台を観ながらではなぜ彼らは演劇というジャンルで表現活動をしているのか、なぜ演劇でなければならなかったのかということを考えさせられた。 我々が自明のごとく見聞きしたり用いる言説は多く、こと舞台芸術に関してはパフォーマンスがその一つに挙げることができるが、改めて吟味すると何とも曖昧模糊としている。演じ手が居てそれを見る者が同席することで共に生成するその時、その場の唯一無二の親和的宇宙を開示する見せ物が演劇の原初的な在り処である。ならばパフォーマンスもそういった演劇の枠内に収まるものであるはずであるがそうならずに別の印象を自動的に誘発されてしまう。すなわち身体言語を上位概念と捕えてなされる演劇の解体であり、そこから容易く前衛的なるものの匂いを嗅ぎ取ってしまうのだ。今作が所見のdots『MONU/MENT(s) for Living』もパフォーマンス・グループと自らを位置付けているようにしっかりパフォーマンスを展開していた。
我々が自明のごとく見聞きしたり用いる言説は多く、こと舞台芸術に関してはパフォーマンスがその一つに挙げることができるが、改めて吟味すると何とも曖昧模糊としている。演じ手が居てそれを見る者が同席することで共に生成するその時、その場の唯一無二の親和的宇宙を開示する見せ物が演劇の原初的な在り処である。ならばパフォーマンスもそういった演劇の枠内に収まるものであるはずであるがそうならずに別の印象を自動的に誘発されてしまう。すなわち身体言語を上位概念と捕えてなされる演劇の解体であり、そこから容易く前衛的なるものの匂いを嗅ぎ取ってしまうのだ。今作が所見のdots『MONU/MENT(s) for Living』もパフォーマンス・グループと自らを位置付けているようにしっかりパフォーマンスを展開していた。