◎相互理解への疑義と不信 観客の挑発から次なるステージを
藤原央登(「 現在形の批評 」主宰)
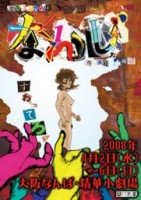 開演前の劇場で流れていた尾崎紀世彦の『また会う日まで』。客入れ音楽のみならず、随所に挿入歌として使用される歌謡曲が未経験のノスタルジーを喚起し、それと共に原色鮮やかな照明と有り余る身体の力をバカバカしい笑いとギャグへ接続して駆け抜けてゆく悪い芝居の劇世界は、そのセンスの良さに反し、演劇を志向する自己と刹那の享楽を求めて観客席に座る我々への冷めた視線によって早くも一つの文体を獲得している。この根底に流れる基本テーゼこそ、この集団が他の若い集団と峻別した意識の高さの発露となっているのだが、舞台を観ながらではなぜ彼らは演劇というジャンルで表現活動をしているのか、なぜ演劇でなければならなかったのかということを考えさせられた。
開演前の劇場で流れていた尾崎紀世彦の『また会う日まで』。客入れ音楽のみならず、随所に挿入歌として使用される歌謡曲が未経験のノスタルジーを喚起し、それと共に原色鮮やかな照明と有り余る身体の力をバカバカしい笑いとギャグへ接続して駆け抜けてゆく悪い芝居の劇世界は、そのセンスの良さに反し、演劇を志向する自己と刹那の享楽を求めて観客席に座る我々への冷めた視線によって早くも一つの文体を獲得している。この根底に流れる基本テーゼこそ、この集団が他の若い集団と峻別した意識の高さの発露となっているのだが、舞台を観ながらではなぜ彼らは演劇というジャンルで表現活動をしているのか、なぜ演劇でなければならなかったのかということを考えさせられた。
演劇活動をしていると必ずと言って良いほどぶち当たるのは「別に演劇などなくても世界に影響がない」という社会通念が長らく蔓延させる諦念である。演劇を巡る状況と歴史はそれ故、社会変革への起爆剤として先鋭化しては挫折を繰り返す過程を描く闘争劇のようである。演劇に携わろうとする者に差し迫った厳しい問題にも関わらず、その枠内に収斂することを無批判に信じきって、粛々と執り行われる軟弱な作品で溢れかえっている。悪い芝居の作品・俳優から滲み出る自己批判を含めた冷めた視線という、演劇をあえて引き受けようとする者に要請される自覚的意思はだから特異であるとすら言えるのだ。
物語はなかなか始まらない。役者もこなす作・演出の山崎彬がセーラー服姿で客席後方からやって来て激しく叫び、悪態をつく。客席に居る私たちに決して微温的な内容ではなかったように思うが明瞭に何を話していたかは、バックに流れる音楽のせいもあって思い出せない。ただ、目をむき出しにして開き、あらん限りの声でがなりたてて喋る山崎の悪態に、「インターネットで好きなことを書けば良い」という発言が出た時、少なくともこれまで二本の劇評を書いている私に向けられた挑戦であり、挑発ではないかと思った。
と同時に、この集団に私が注目してきた基本テーゼが、単なるシニシズムに染められたものではなく、もちろん戯曲世界が形成する物語に同調する観客を慰撫する一人称のモノローグしか構築し得ないつまらない世界でもない、言ってみれば対話を希求し、舞台と客席の間に引き起こそうとする欲望に支えられているのではないか。上位下達式に主義主張を伝播させ、移入させる一方的なものよりかは、物語構造の規格外から直接投げ出される本音とも取れる声と人を食ったような演劇構造を逆手に取る仕掛けは、観客とのインタラクティブで雑多なコミュニケーションの矢をぐるぐると渦巻かすことが可能になる。
悪い芝居の方法は、何者をも信用しないメンタリティーからしか醸成され得ないものだろう。これまでの作品にも共通する要素に、リビドーがある。現在ここにいる私達とは、精子と卵子が受精した受精卵が基となっている。それはいわば、無責任なセックスで無理矢理生み出された存在であるとすれば無意味であるという観念。人間を、いや生物を遡及してみれば皆平等な一個の受精卵でしかないはずが、個体成長につれて人間の良し悪しが判定されてしまう不合理。不合理な存在だからこそ、その決定の準拠枠も何を根拠になされているのか判然とせず、なんとなく社会を覆う常識という名の通念によって突き動かされ、時にそれに従わざるを得ないもどかしさが生じる。
悪い芝居にとってのリビドーとは、単なる作品を引き立てる笑いの道具としてではなく、人間の根底に存在する不合理の象徴としてあるのだ。今作に沿えば、常に主役として人々の注目を浴びていたい独占欲の塊である姉と、誘拐されたことによってマスメディアでその行方がクローズアップされ、主役に引き立てられてしまった妹という、腹違いの姉妹の存在によって示されている。この姉妹の物語と、10年後の自分達へ宛ててタイムカプセルを埋める、姉と同級生の男子中学生達の物語が絡むことが大筋を成す。舞台を貫通するのは「いくら思っても君との距離が縮まらない」という台詞が示すように、他者理解のための絶対的な安定構造の不信にある。他者へ対する想いを捧げるため手を胸に合わせて祈る姿勢が、喉元へ突きつけた匕首による自傷行為へと見立ててしまう辺りはなかなかシニカルである。演劇の約束事を平気で破って笑いに変えて遊んでしまうスタイルの湧出点は、こういった立場に依拠していることが了解される。
人と人、人と社会が凹凸をぴたりと嵌まるように相互理解することへの疑義。社会構造の強固であると目されたシステムが建前でしかないことが判明し、我が身一つで閉塞した状況を打開するか諦念してドロップアウトするかを選択しなければならなくなった今、その自己自身すらどこまで信用できるのかという問題がまさに匕首となって突きつけられている。「夢オチならいいのに」という終わり方は、創作者と観客が単一の相互理解に円環して自閉してしまう演劇の虚構性の無意味さを嫌悪する現実主義的とも言えるこの集団の性格がよく顕れている。直接我々に言葉を投げ出し挑発するエネルギッシュで明るい作風は、オタク感性をポップに味付けしてショーアップするだけのものとは異なっている。さらに、オタク感性で言えば、3月に観劇した五反田団『偉大なる生活の冒険』は文学資質による細密画的手法で、退廃的な若者の生活様態を描いた。静謐且つしたたかな戦略上、その射程は遅速にならざるを得ず、悪い芝居とは対極に位置するものの、観客内部へ生理的嫌悪を引き起こし、舞台内世界との同質性の喚起を引き起こす腕力の強さの近似性を抽出できる。そして、私はそういった作品に大いに共感するのだ。
と、ここまで書き進めてきてではなぜ演劇に拘泥するのか、その主張がまだ明確に感じられない。現実主義的な冷めた視線はいわば山崎彬と悪い芝居の現状認識、あるいは倫理規範である。私は確かにその点には大きく関心しているのだが、それを維持しつつその地点から次なるステージへの展開を図ることを模索しなければ、これまでの方法がスタイルとして制度固着し消費されやがて無害なものに帰してしまうだろう。直接芸術としての演劇の特性に甘んじた馴れ合いの関係性を否定することから、観客を挑発することから独自の対話を舞台の間に創生させることができるかは、次の仕掛けが必要ではないか。(4月5日 精華小劇場 マチネ)
(初出:週刊マガジン・ワンダーランド 第90号、2008年4月16日発行。購読は登録ページから)
【著者紹介】
藤原央登 (ふじわら・ひさと) 1983年大阪府生まれ。近畿大学演劇・芸能専攻卒業。劇評ブログ『 現在形の批評 』主宰。Wonderland 執筆メンバー。国際演劇評論家協会会員。
・Wonderland寄稿一覧:http://www.wonderlands.jp/archives/category/ha/fujiwara-hisato/
【上演記録】
悪い芝居『なんじ』
精華小劇場(2008年4月2日-6日)
【作・演出】山崎彬
【出演】
吉川莉早
三國ゲナン
四宮章吾
大川原瑞穂
藤代敬弘
植田順平
梅田眞千子
森本児太郎
山崎彬
【スタッフ】
舞台監督:小島聡太
美術:丸山ともき
大道具:津田郁久
照明:真田貴吉
音響:中野千弘
映像:竹崎博人
衣装・メイク:西岡未央
小道具:藤代敬弘・四宮章吾
宣伝美術:SAYONARA女学園
演出助手:鈴木トオル
WEB:植田順平
広報:井上かほり
制作部:田浦明子
制作:中栄遊子
一般 前売 2,000円 当日 2,300円 学生 前売 1,500円 当日 1,800円 前夜祭特別価格 1,500円
アフタートーク「おないどし」
4月5日(土)14時の回終演後
出演:山崎彬(悪い芝居)×橋本匡(尼崎ロマンポルノ)
【主催】:精華演劇祭実行委員会/悪い芝居
【共催】:NPO法人京都舞台芸術協会
【企画】・制作:悪い芝居