◎「気配」をホラーに変える演劇 観客も不安や怯えとシンクロ
木俣冬(フリーライター)
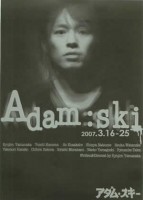 気配の演劇だなと思った。
気配の演劇だなと思った。
Jホラーというジャンルがブームになって久しいが、その代表格の『女優霊』を“気配の恐怖”だと中田秀夫監督は当時解説していたと記憶する。そもそも、日本人は日本家屋の突き当たりの薄暗い納戸や階段の上など、そこに何かが潜んでいるようなコワサ、どこかからのぞかれているかもしれないコワサに敏感だ。日本人特有の民俗感をくすぐることでJホラーは巨大なムーブメントとなった。
スロウライダーは、結成(2001年)から一貫して、ホラーをモチーフにした演劇をつくってきた。すべてを見てきたわけではないが、彼らの言うところのホラーを私は、単なる怪物や幽霊が出てきてコワイということではなくて、日常の中でふとした瞬間、足を滑らせて落ち込んでしまう感情の断層の暗がりを描いていてコワイという、正当派なホラーのたたずまいをもった作品だと受け止めてきた。もちろん怪物や幽霊を期待する人たちも満足、ちゃんと怪物とか幽霊は出てくる。姿は見えないが、穴の中に、家の奥に、それらは蠢いている。たとえば、『わるくち草原の見はり塔』(2004年)では、収容所のある草原の穴の中に女の化け物がいて収容者たちが次々食われてしまう。『トカゲを釣る』(2005年)では蝸牛という怪物がアパートの地下に飼われていて、それはアパートの住人の感情と共生しているらしいという設定だった。
今回の『Adam:ski』では、亡くなった民俗学者・折口信夫の気配が残された弟子たちを脅かす。
弟子たちは4人。それぞれが亡くなった師の自伝のゴーストライターをやっているが、皆の師に対する印象がバラバラで、原稿に一貫性がないと編集者に指摘されてしまう。
弟子達は皆、自分こそ真実を書きたいと願っている。折口の愛人・生萩(山口奈緒子)は、女の目から見た男・折口の姿を書かせたいと、ひとりの弟子・徳田(夏目慎也)に肩入れする。訪れた折口の熱狂的信奉者・別府(竹井亮介)も自分なりの折口像をもっていて、生萩のせいで折口の才能はなくなったと憎んでいる。やがて、ひとり代表して自伝を書く者が選ばれる。選ばれた吉松(金子岳憲)は折口の霊を自分に宿らせて書こうと試みる。それは師が研究していたモドキの原理(人間が神のマネをすることで神に近づく行為。たとえば人間が稀人〈神〉であるナマハゲなどの衣裳を着るとトランス状態になる)に近い行為だった。折口の着物を着て執筆に励む吉松は次第に折口のような言動をはじめる。弟子間の、春洋(日下部そう)と指宿(板倉チヒロ)が先輩格で徳田と吉松はドレイ扱いという序列の崩壊に伴い、折口の屋敷に集う人間関係は急激に不安定なものになっていく。
そして弟子達は謎の死を遂げていき、残ったのは徳田と吉松だけになった。彼らを死に追いやったのは誰なのか? 屋敷の中に異常発生しだした蛾が意味するものは? クライマックス、吉松は折口の口調で徳田に「おまえが自伝を書け」と言う。
物語が進行する中、舞台上には様々な気配が現れては消えていき、登場人物の不安や怯えと観客の興味はシンクロしていく。
舞台はプロセニアムではなく、劇場の半分くらいまで折口信夫の書斎のセットで占められている。階段上になった観客席は上手と下手に斜めにLの字に並び、書斎の隅々まで見渡せる。上手側の窓の向こうの庭、下手奥のドアの向こう、部屋の中央の折口の机の下、その脇などなど、気配はあちこちに仕掛けられている。ドアの横の柱にかかった折口が研究していたナマハゲのような稀人の衣裳も奇妙な気配を漂わせる。さらには、蛾を駆除に来た業者・二宮(村上聡一)と生萩との会話から、家の天井や床下の暗闇も観客の脳裏にじわじわと広がっていく。
結果から言えば、この話は徳田のつくったものだったということで、途中に徳田の見る奇妙な夢が出てくることから観客の一部は早くにそのオチに気づいてしまう。物語を楽しみたい観客にはそこが物足りなさかもしれないが、仕掛けを楽しみたい観客にはエンターテインメントとして充分なサービスがなされていたと思う。
昭和初期風なインテリアを再現した舞台美術(福田暢秀)の細やかさ然り、俳優たちの細やかな芝居然り。単なる脅かしの演劇ではなく、それぞれの人間関係のわだかまりや、個々の立ち位置の不安などが、折口信夫の霊となって屋敷に漂っていたと言ってもいいと現実主義者の私には考えてしまうのだが、それが説得力をもつリアルな演技を各自がしていた。生萩と徳田がつきあっていることがふたりだけの秘密になっているため、徳田と吉松が生萩のことを話し合っている時の徳田の嘘だとか、弟子同士が牽制しあう会話や、この話の語り部である、白崎(山中隆次郎)と編集者・寺居(數間優一)の折口に対する温度差のある会話などのセンスがいい。




余談だが、作家、演出家の書く男達には、男性作家によくある男同士の友情はほとんどなく、大抵みんなイジワルだ。どこか女性同士の感覚に近い。折口のかつての恋人の名前をもらったという春洋役のスロウライダー常連・日下部そうは、山中特有の得体の知れない冷酷さを常に体現している。日下部は普通なら美形俳優で通用するのに、その美しい風貌にまったく頼ってない佇まいにも無軌道な恐怖を思わせる。今回も、師に絡めとられた葛藤を紋切り型でなく演じた。
他に俳優で注目したいのは吉松役の金子岳憲。最初のナチュラルな芝居から、次第にピュアさと狂気の振幅を大きくしていき、観客を大いに攪乱した。また、舞台という作り物の屋敷に長い時間生活していた雰囲気を出すという当たり前のようでなかなか難しいことをサラリとやってみせた。彼がドアから入ってくることで、ドアの向こうの世界が存在しているように思えるのだ。それがなければ、この作品の重要な気配のひとつはなくなっていただろう。
山中が「モドキ」を採り上げたことは、演劇が基本的に「モドキ」(真似を本物に見せる)であるということも含んでいるのだろうか。金子の身体表現には「モドキ」の精神を感じた。この作品が2003年の第三回劇団公演『アダム・スキー』を大幅に改訂したもので初期作品であることが、演じるという行為の基本に向き合っていた頃だとしたら納得もいく。
山中が、折口信夫の魂を自らの身体に宿すことを「インストールする」という言葉を使ったのも面白い。他にも「レイヤー」(コスプレーヤー)とかアニメ、ゲーム文化的用語がサラリと出てくる。洋風の日本家屋と家具というクラシカルな部屋、寄生(これもある種のモドキ、インストール行為)の象徴・蛾という古典的なイメージと、平成型の若者たちの風俗が混じり合う異和感までもが、山中のつくり出す恐怖の断層のようにも思えてくる。
しかしそれはどこまで意識的なのかはわからない。たとえば、冒頭、部外者として折口家の人々の話を聞いていた寺居が、窓にへばりついた蛾を見て「年とってから急に(虫が)気持ち悪くなっちゃって…」と言ってかすかに腕を掻くことは、これからはじまる異様な世界に足を踏み入れた最初の合図に見える。次第に物語という怪物に寄生されていく感情を体を掻くという行為で示す。最初はかすかに、次第に大きく掻いていくことは効果的でもあるが、もうひねり新しい表現を探せなかっただろうか?というもどかしさも否めない。散りばめられた断片のすべてに神経が行き届ききった時、作品として骨太になるように思う。アニメやゲーム、Jホラー風俗の「モドキ」はアイテムをマネするとソレっぽくはなるのだが、ホンモノになるには相当の技術が必要なのである。『機動戦士ガンダム』と『新世紀エヴァンゲリオン』の関係、それ以降のエヴァモドキ作品の関係みたいなものと言えば、わかって頂ける人にはわかって頂けると思う。
さて、スロウライダーは演劇界では、日常生活の中の関係性、会話を丹念に表現する演劇を追求する、いわゆるアゴラ一派に数えられている。平田オリザ作品の洗礼を受けた20代-30代前半の現代口語派は、ポツドールの「セックス」、五反田団の「貧乏」、乞局の「ブラック・ジャーナリズム的なもの」などのキーワード、チェルフィッチュのコンテンポラリーダンスのような言動の記号化など、それぞれ持ち味をつくり新たな現代のスケッチを模索しているが、スロウライダーが選んだのはホラーだった。
これら現代口語演劇で重視される、会話と会話の間の語られない部分を「気配」と呼んでみる。山中はその気配をホラーへと変化させた。山中はその気配をゆっくり静かに見せるのではなく、逆にイヤな気配が立ち上ってくる断層に足を滑らせまいとするかのように、俳優たちを猛スピードでラストまで駆けさせる。その断層には自分や他者の悪感情という怪物が牙をむいているのだから無理もない。映像だと気配の画づくりをすればいいが、演劇では俳優たちが芝居で気配の断層をつくらなくてはいけない。ラストの白崎の一言「生萩」(白崎の妻が生萩だった)のために、皆が断層に落ちずにゴールまで登りつめなくてはいけない。これもある意味、神の域に近づく行為なのかもしれない。
ちょっとした互いのかみ合わせのズレが気配を小さくしてしまうというスリル…! こうしてスロウライダーの気配の恐怖は一段と際立っていく。
最後にもうひとつ。この作品は、折口信夫がナマハゲという稀人の名前をもじってつけた特別なオンナ「生萩」が折口信夫の真実を伝えようと、弟子のひとり徳田を選び、またその徳田がつくった物語を白崎に伝えてもらうために寄生しているという恐怖の連鎖(『リング』みたいだ)を突きつける。が、そのためにも女優には圧倒的な魔性感が欲しかった。普通のカワイイ女性なので女性と恋して神から人間になった折口が不幸だったのか幸せだったのかという問いの印象が薄まってしまうのが惜しい。
怪優系の男性が多い小劇場に、巫女的な女優の降臨を期待したい。
(初出:週刊「マガジン・ワンダーランド」第38号、2007年4月18日発行。購読は登録ページから)
【筆者紹介】
木俣冬(きまた・ふゆ)
フリーライター。映画、演劇の二毛作で、パンフレットや関連書籍の企画、編集、取材などを行う。キネマ旬報社「アクチュール」にて、俳優ルポルタージュ「挑戦者たち」連載中。蜷川幸雄と演劇を作るスタッフ、キャストの様子をドキュメンタリーするサイトNinagawa Studio(ニナガワ・スタジオ)を運営中。
個人ブログ「紙と波」(http://blog.livedoor.jp/kamitonami/)
【上演記録】
スロウライダー第9回公演「Adam:ski」(アダム・スキー)
http://www.slowrider.net/
作・演出 山中隆次郎
三鷹市芸術文化センター星のホール(3月16日-25日 2007年)
【出演】
山中隆次郎
數間優一
日下部そう(ポかリン記憶舎)
夏目慎也(東京デスロック)
渡辺いつか
金子岳憲(ハイバイ)
板倉チヒロ(クロムモリブデン)
村上聡一(中野成樹十フランケンズ)
山口奈緒子(明日図鑑)
竹井亮介(親族代表)
【スタツフ】
舞台美術/福田暢秀 (F・A・T STUDIO)
照明/伊藤孝 (ART CORE design)
照明操作/三浦詩織
音響/中村嘉宏 (atSound)
音響操作/井川佳代
舞台監督/西廣 奏
舞台監督補佐/シロサキユウジ
宣伝美術/土谷 朋子 (citron works)
宣伝・記録写真/西田航
記録映像/トリックスターフィルム
WEB運営/栗栖義臣
制作補佐/坂本 明
制作/三好佐智子
企画・製作/有限会社quinada
主催/(財)三鷹市芸術文化振興財団
協カ/ポかリン記憶舎、東京デスロック、ハイバイ、クロムモリプデン、中野琳釘十フランケンズ、明日図鑑、親族代表、krei・inc、㈱リコモーション、小栗永理子、中村成志、佐藤こぅじ、帯瀬運送㈱
☆終演後、脚本・演出家山中隆次郎と以下の出演者との対談。
16日/タニノ クロウ(庭劇団ペニノ主宰)
20日/高橋 洋(脚本家・映画監督)
21日/古澤 健(映画監督)
22日/高橋敏夫(文芸評論家・早稲田大学文学部教授)
23日/冨永昌敬(映画監督)
【全席指定】
[前売] 会員=2,500円 一般=2,800円
[当日] 会員=2,800円 一般=3,000円
高校生以下=1,000円(前売・当日とも)