◎「現在にふれるために未来へ疾走せよ」に乗れないのはなぜか?
~ままごと『わが星』を批判する~
西川泰功
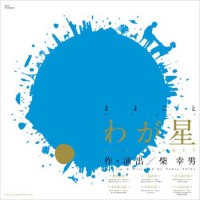 第54回岸田國士戯曲賞を受賞した柴幸男作『わが星』が、三鷹市芸術文化センター星のホールで再演されました。特にツイッター上では、この作品の「褒め言葉」が溢れており、ほとんど「奇妙な」と言っていいほどのその盛況に違和感を抱かずにはいられません。ぼくは、この作品が「新しい」とも「今だからこそ」とも「気持ちいい」とも思わなかったのですが、ただ何かしら感動的なものを含んでいることは確かで、そのことについて書いておきたいと思います。そのために、感動的だと思わない要素を、ひとつひとつ捨てていきたい。ここでぼくが捨ててゆく要素に、多くの人が感動しているのだとしたら、そのことを批判したいからです。そして最後に、この作品の真に感動的だと思われることにだけ、ぼくなりの光を当て、しかしその美点をも作品自体が裏切っていることを付け加えたいと思います。
第54回岸田國士戯曲賞を受賞した柴幸男作『わが星』が、三鷹市芸術文化センター星のホールで再演されました。特にツイッター上では、この作品の「褒め言葉」が溢れており、ほとんど「奇妙な」と言っていいほどのその盛況に違和感を抱かずにはいられません。ぼくは、この作品が「新しい」とも「今だからこそ」とも「気持ちいい」とも思わなかったのですが、ただ何かしら感動的なものを含んでいることは確かで、そのことについて書いておきたいと思います。そのために、感動的だと思わない要素を、ひとつひとつ捨てていきたい。ここでぼくが捨ててゆく要素に、多くの人が感動しているのだとしたら、そのことを批判したいからです。そして最後に、この作品の真に感動的だと思われることにだけ、ぼくなりの光を当て、しかしその美点をも作品自体が裏切っていることを付け加えたいと思います。
まず、この作品のもっとも野心的な試みであるところの、リズムを劇の推進力として用いている点について、指摘したいと思います。おそらくこの試みがある程度成功しているために、多くの人の心を動かしたと言えるでしょう。この作品は、作者自身が言うように日本語ラップを応用し、韻をふみ、台詞の字数を規則的にすることで、劇をリズミカルに運ぶことに苦心されています。劇のほぼ全編を通して、同じリズムのビートが打たれる中、俳優がそれに合わせて台詞を発する。台詞がこのビートへの依存度を高めると、パフォーマンスは音楽に近づき、その極致で俳優は踊ります。この芝居と音楽のレンジを行き来するダイナミズムによって、作品はみずみずしい躍動感を得ることになる。また、こうした構造にともない、同じようなシーンが繰り返される(時間の経過や台詞上のズレがあるにしても)という作劇上の手法も、このダイナミズムを生み出すことに加担しています。劇全体がリズムと反復によって支配されているわけです。80分という上演時間の間、一定のリズムが刻まれるという、ほとんどトランスを促す劇場空間の中で、「イッてしまう人」が多いのは当然というべきかもしれません。
ぼくはこの試みをまず否定したいと思う。というのも「演劇はこういうものではない」と考えるからです。本作の岸田戯曲賞選評で、劇作家の宮沢章夫が指摘しているように(註1)、日本の現代演劇はもはや「アンチテアトルであること」を求めていないのかもしれませんし、むしろその背景のために本作が高い評価を得ていると言えるでしょう。
しかし、「アンチテアトルでない」とはどういうことでしょうか。それは「アンチ・アンチテアトル」≒「テアトル」に、意図せずに近づく「危険」を孕んでいるということです。なぜ歴史が「アンチテアトル」を要請したか。「テアトル」の同化作用への批判意識が創作を衝き動かしたからです。「演劇は批評を内包していなければならない」。大袈裟に言えば、これが歴史的な命題になりました。ブレヒトの「異化」とアルトーの「残酷」をはじめ、未だにその範疇のなかで繰り返される演劇創作にまつわる思考が、それを物語っています。
ついでに言えば、作者が影響を受けたと言うソーントン・ワールダー作『わが町』における舞台監督と町の人々との位相を変える趣向もこの範疇に含まれます。この観点から『わが星』のリズムへの試みを支持できません。それは一言で言ってしまえば、否応無く観客を劇へ巻き込むための方法だからです。それがいくら手法の洗練度において優れているとしても、その作用における煽動効果を受け入れるわけにはいきません。20世紀の偉大な演劇人が苦心して創作に織り込んできた演劇自身への批判を、演劇史の先端にありながら、また岸田戯曲賞という権威を携えながら、引き受けないというよりは忘れてしまったというような態度を、容認するわけにはいきません。(もっとも歴史を無視するのは日本演劇界に限ってのことではなく、特に日本の現代美術の分野で頻繁に指摘されることですが。)

2番目に、本作が再演されたこの時期ということを考えたいと思います。言うまでもなく2011年3月11日の東北を中心とする東日本を襲った大地震と、併発した福島原子力発電所事故の影響は甚大で、想像力の分野にも深い変動をもたらすと思われます。『わが星』はこの大地震から約1ヶ月後、2011年4月15日から再演の公演を開始しました。劇の内容が直接的に震災や原発事故と関係がないとしても、悲惨な現状をこの劇に重ねた観客も多かったのではないかと想像します。というのも、『わが星』では、太陽が近づいてきて地球が滅亡するという歴史的な時間のなかで生きる家族の様子が描かれているからです。破滅的な状況を前にした家族の物語。こう捉えると、まさに大震災後の今、無数に発生する問題を抱えながら生きている多くの人たちの姿がオーバーラップするとしても不思議ではありません。観客の熱狂的な支持の背景にはこういった現状への共振があると思われます。
しかし、これもぼくは否定しておきたい。というのも、『わが星』に出てくる家族は大変に明るく、屈託なく、諦念というよりは無関心を携えて、自らの死に対峙しているように見えたからです。端的に言って「ちょっとはあがけよ」と思うわけです。こうした無関心の明るさを持った家族が、アイロニーではなく、率直に肯定的に描かれ、それが受け入れられるという状況に不安を抱きました。決定的な破壊を前にして、心に澱みというものが感じられなかったのです。そんな「無関心の聖人」の顔をして、なぜ死んでゆけるのでしょう。もしここに登場する家族が、震災により様々に苦しまれている人たちに重ねられて観劇されているとしたら、それは大変に失礼だと言う他ありません。これは創作者へのというよりはむしろ観劇リテラシーにおける批判です。
3番目に、ここに出てくる登場人物たちの明るさが気持ちいいのだ、という意見があると思います。なるほど確かにここに出てくる家族は非常に仲がよく、また主人公と言ってもいい存在感の次女ちーちゃんとその友人つきとの関係も良好で、人間関係を壊すものが描かれていない。無傷な良好さのみが浮かび上がるようになっている。こういう関係性に憧憬を抱くということがあります。ちーちゃんの誕生日を祝うシーンを例にとります。このシーンは繰り返されますが、そのなかでも「リモコン付きテレビ/鉛筆ブーム」、「衛星放送/ロケット鉛筆ブーム」、「地デジ/ロケットブーム」というように一部の台詞が置き換わり、時代の変化をしのばせている。またこの繰り返しに自転、公転といった宇宙規模の運動を重ね合わせてもいます。
しかし、肝心なこのシーンの印象といえば、どの時代にも存在しなかった幸福すぎる家族像が現代の眼から創造されているかのようです。ノスタルジーと言ってもいい。後述しますが、時間を意識的に扱いながら、無時間の空間をつくりあげてしまう感性は、実はこの作品の本質的な内容と矛盾しています。
またセカイ系批判の文脈でも批判しておきたい。「セカイ系」とは、自己とその愛する対象の間に中間項を挟まない、という創作手法を指摘する批評言語です。ここでは、多くの場合、「君とぼく」だけが強固な現実感として描かれます。それを滅ぼすものといえば、「君」や「ぼく」と対等な存在ではなく、「世界の滅亡」であったりする。つまり、「君とぼく」の力ではどうにも成り得ないものが破壊のシンボルになっており、裏返せば、それ以外の、対等に向い合い複雑な局面を交渉するような状況は排除されているのです。これは何を意味するかと言えば、「君とぼく」の関係だけが唯一の関係であり、それが壊れれば世界も同時に壊れてしまうという、大変に脆い世界観だということです。人間関係に批評性が介入しない。
『わが星』で描かれる人間関係はこれに似ています。みんなが仲良しで、ただそれだけなのです。そして批評性というには大き過ぎる、地球の滅亡という出来事が特別な位置に置かれており、この壊滅的な死の局面でも誰も苦しまない。生き延びようと苦心しない。みんなで滅びてゆくのです。仲のよい家族に、友人関係に、憧れるのはわかりますが、そうした「日常」が大切だと主張する人が(ぼくもその一人です)、果たしてこんな死を描いていいのでしょうか。あるいは、こんな死に感動していいのでしょうか。
最後に、『わが星』はソーントン・ワイルダー作『わが町』の翻案だ、という考えについて触れておきたいと思います。岸田戯曲賞の選評で劇作家の鴻上尚史が「『わが町』の感動を借りている」と指摘しましたし(註2)、ユリイカ2010年9月号で舞台芸術批評の内野儀が「翻案だ」と言い切りました(註3)。また岸田戯曲賞受賞後に刊行された戯曲本のあとがきで、作者自身が本作はワイルダーの世界観に影響されていると明言しています。その意味で翻案物であると言っていいと思います。しかし、本当に本作が「『わが町』の感動を借りている」のかには疑問が残ります。その「感動」は翻案物らしく、微妙にズラされているのではないか。この点の考察を通して、ぼくがこの作品で真に感動的だと思ったことについて書きとめたいと思います。
『わが星』はその劇進行においても、そう言ってよければ思想においても、次のことをモチーフとしています。それは「現在に触れるためには未来へ疾走しなくてはならない」という認識です。説明します。男が、20年後に先生になった自分自身と話すシーンがあります。このシーンで、男が、望遠鏡から見えている星に向って進むことに決める。普通に考えれば、その星に到達したときすでに星は消滅しているはずです。あるいは仮に光の速度を越えてその星に到達できたとしても、その直後に目の前で星が消滅してしまう。それでもこの男は星に向うのです。このシーンではまだ、その星が「誰」であるかということはわかりませんし、そもそも「誰か」などと考える余裕を与えてくれませんが、最後に、男が地球滅亡寸前の(つまり死ぬ直前の)ちーちゃんと出会うというシーンが用意されており、この男が見ていた星がちーちゃんだったと、観客は知ることになる。
星の光は何億年も前に消失した星のそれだという、光の速度に関する時間的なトリックを、人間同士が近づくという存在論的な問題の寓意として用いているのです。星の輝きは人の生命の寓意です。男には光が見えている。見えているものには近づけると思う。しかし、それに出会うためには光の速度を超えなければならない。超えて出会っても、それは一瞬のことなのです。ここではそのようなものとして出会いが描かれている。出会う一瞬という時間が、人間に実現可能な速度を超えた上に成立する奇跡として特別化される。これは誰にとっても不思議なこととして浮かび上がります。なぜなら眼の前の彼が、彼女が、見えているならば、その光は、眼の前の彼や彼女がいる位置から、時間的な遅れをともなって、見る者の眼に届いているのですから。見えている世界はいつも過去なのです。だからそこにいる彼や彼女に到達するためには、いつも未来を目指さなくてはいけない。現在は光の速度の向こう側にある。とすると、出会いとは現在に触れるための未来への疾走です。これがこの作品の思想と言っていいと思います。
では、ワイルダーの『わが町』はどこに思想を孕んでいたでしょうか。それは第3幕、死者となったエミリが12歳の自分の誕生日に戻るシーンです。エミリは生きている者の速度に耐えられない。生を外側から見るという、死者としての静的な視点を持った彼女は、生きるということのめまぐるしい速度についていけないわけです。この構造によって、アイロニックに言えば「生者の無反省」を、また率直に言えば「生活の愛おしさ」を照射してみせる。ここに『わが町』の思想があったはずです。ここには決して越えられない壁、絶対的な時間の相違として、生死の境がありました。エミリは過去に戻ろうとした。ここで出会いは過去への疾走でした。ところが、生者の現実が開示したとき、エミリは出会いにはじかれてしまう。エミリは後悔します。過去へ疾走しても出会いは成就しないのです。
『わが星』では、この壁に相当する男とちーちゃんの境界が越えられます。ここにも絶対的な時間の相違があったはずです。ちーちゃんは男にとって何億光年も先の星の光なのですから。しかしほんの一瞬だけだったとしても、男はちーちゃんに出会う。その出会いはまぎれもなく喜びを抱かせます。男は、エミリのように後悔しない。出会いをついに恐れることがない。つまり『わが星』は、『わが町』で失敗したエミリの出会いを、時間の方向を真逆に進ませることで、成功させたのです。現在へ触れるために過去へ疾走しても、出会いは起こらない。未来へ疾走せよ、と。
これにはいいも悪いもありません。この出会いは、現在に触れたときにだけ感じられる、関係の「死」を条件にした存在同士のこそばゆい衝突のようなものですから。この衝突の感触を人は求めるものだし、それによって生がにわかな喜びとともにあがなわれる。その意味で、これは生きることにおいて必要不可欠の、何事かなのです。これを浮かび上がらせ、感じさせたということが、この作品のもっとも優れた点であり、真に感動的なことなのだと、ぼくは考えます。
そして最後の最後に、保留しておいた矛盾について書きます。この「現在に触れるための未来への疾走」は、その時間についての感性とは裏腹に、劇全体の印象としての無時間性と矛盾します。「現在に触れるための未来への疾走」は、先に記したように絵空事ではなく、この現実のなかに確かに息づく感触として感じられる。その感触を、劇全体の無時間的な印象が裏切っていないか。なぜなら「未来への疾走」は、その先にある「現在」にコツンと衝突する、その感触のためにあるはずだからです。それなのに、あたかもどんな苦悩も、どんな矛盾も、どんな衝突も抱えずに、「未来への疾走」の感触だけが確かなものとしてすでにある。まるで他の何に対しても不感症であるような、そんな潔癖の自己防御のような世界のなかで、一点血が通うのが「未来への疾走」だけである。そんな印象を与えるからです。それで本当に、その先にあるはずの「現在」に手が届くのか。この走り方で届くのかよ、と思うわけです。「時間を意識的に扱いながら、無時間の空間をつくりあげてしまう感性が、この作品の本質的な内容と矛盾している」とはそういうことです。だから、最終的に、ぼくは乗れないのです。
註1・註2:http://www.hakusuisha.co.jp/kishida/review54.php(最終アクセス日2011年4月26日)
註3:同書掲載、内野儀「10年代の上演系芸術 ヨーロッパの「田舎」をやめることについて」
(初出:マガジン・ワンダーランド第240号、2011年5月11日発行。無料購読は登録ページから)
【筆者略歴】
西川泰功(にしかわ・やすのり)
1986年山口県生まれ。下関市民、厚木市民、世田谷区民を経て、2009年4月より静岡市民。SPAC(財団法人静岡県舞台芸術センター)でテキスト作成等の業務に携わりながら、ライフワークとしてフィクション創作に従事。「西河真功」名義で書いた小説『懐妊祝い』で第23回早稲田文学新人賞最終候補。ブログ「妊婦/忍者」をたまに更新します。
【上演記録】
ままごと『わが星』
【東京公演】三鷹市芸術文化センター星のホール(2011年4月15日-5月1日)
【三重公演】三重県文化会館 中ホール 特設舞台(5月7日-8日)
【名古屋公演】千草文化小劇場(5月12日-13日)
【北九州公演】北九州芸術劇場 小劇場(5月19日-22日)
【伊丹公演】AI-HALL(5月27日-29日)
作・演出・演奏:柴幸男
出演
青木宏幸、大柿友哉(害獣芝居)、黒岩三佳(あひるなんちゃら)、斎藤淳子(中野成樹+フランケンズ)、永井秀樹(青年団)、中島佳子、端田新菜(青年団)、三浦俊輔
スタッフ
音楽:三浦康嗣(口口口)
振付:白神ももこ(モモンガ・コンプレックス)
ドラマトゥルク:野村政之
舞台監督:佐藤恵
演出部:山下翼
演出助手:白川のぞみ(てとあし)
美術:青木拓也
照明:伊藤泰行
照明補佐:富山貴之、南香織
音響:星野大輔
音響補佐:高橋真衣、池田野歩
衣裳:藤谷香子(快快)
写真撮影:青木司
宣伝美術:セキコウ
WEB:CINRA INC,
WEB&Twitter管理:廣野未樹(Unit woi)
制作:ZuQnZ[坂本もも、高橋ゆうこ、林香菜]、森川健太(三鷹市芸術文化振興財団)
制作統括:森元隆樹(三鷹市芸術文化振興財団)
製作総指揮:宮永琢生
特別協力:急な坂スタジオ
協力:こまばアゴラ劇場、舞台美術研究工房 六尺堂、ダックスープ、ロロ、マームとジプシー、LLC10℃、commmons、シバイエンジン
助成:芸術文化振興基金、セゾン文化財団
企画制作:ままごと、ZuQnZ
主催:三鷹市芸術文化振興財団、ままごと
チケット料金:【前売】一般3000円/財団友の会会員2700円【当日】一般3500円/財団友の会会員3150円【高校生以下】前売・当日1000円
助成=公益財団法人セゾン文化財団
レビュー、興味深く拝読しました。
WEB上での絶賛一色の趨勢に真正面から抗うその姿勢に、とても共感します。