◎「14歳の国」(宮沢章夫著 白水社 1998年)
田辺剛
 わたしが初めて自分で戯曲を書き、劇作家として活動を始めようとした頃、どうやって書けばいいのかも分からず見よう見まねでやるほかないと、やる気だけは十分な時に出会った『14歳の国』だ。戯曲の一部を試演しているのを観て興味をもち、本屋を探したのを覚えている。装丁の写真やデザインも印象的だった。
わたしが初めて自分で戯曲を書き、劇作家として活動を始めようとした頃、どうやって書けばいいのかも分からず見よう見まねでやるほかないと、やる気だけは十分な時に出会った『14歳の国』だ。戯曲の一部を試演しているのを観て興味をもち、本屋を探したのを覚えている。装丁の写真やデザインも印象的だった。
この本は本編だけではなく、まえがきやあとがきに加えて「上演の手引き」という文章もあり、いま読み返してみると、単に一本の戯曲というよりも、本全体として著者の演劇論になっているのだと気が付く。そうしたこともあって駆け出しの頃のわたしには特に刺激に満ちていたのだろう。戯曲や演劇への手がかりのようなものをわたしはこの本から得たのだった。
『14歳の国』は、1998年に上演された戯曲だ。中学校の教室を舞台に体育の授業中で生徒が不在であるところに教師たちがやってきて持ち物を調べる。二場構成になっていて、一場では時間が足りずに目的が果たせなかったので、翌週の同じ時間に改めて教師たちがやって来る(二場)という構成である。
学校の教室は、そこで子どもたちを効率よく管理し教育を施すために大人が設えたもののはずだが、それにもかかわらず、大人がよそ者として侵入することでしか入れない「国」がそこにできている。侵入するのは、持ち物検査をしにくる教師たちだ。彼らは学校や生徒を危険から守るという「高邁な精神」と、荷物を調べていることを生徒にバレてはいけないという「こそこそした身体」でもって、そこにいる。
一般に、戯曲にはト書きというカタチでその状況などが補足されはするものの、なぜだか舞台に現れる登場人物が発話したその内容が記されるだけだ。だから読者はその発話されたことばにこそ劇のすべてが詰め込まれているとつい思ってしまうし、書き手にしたって、そのように「台詞」はあらねばならないと考える人はいる。しかし『14歳の国』ではその台詞そのものから「高邁な精神とこそこそした身体」は直接には示されない。よく考えれば当たり前のことだが、台詞は「高邁な精神とこそこそした身体」の結果として発話されたものであって、そのことばの連なりを読者は目の当たりにするだけなのだ。虚構のことばが先にあって身体や世界がそれから生成されるのではなく、虚構の身体と世界がまずあってその残滓としてことばが残され記録されるのである。読者は残されたもの(ことば)から逆に辿って、その劇世界やそこにある身体を想像するしかない。
戯曲には、その劇の世界についてほとんどのことは書かれていないし、そもそも書かれえない。著者が言ったわけではないが、戯曲とはそういうものではないかと『14歳の国』を読んだわたしは思った。
円を示すために、くるっと丸を描くのではなく、その周囲が円ではないことを示すことでかろうじてそれが円であることが伝わるような、そうした表現への臨み方だ。当時、初心者ながら、丸を描いて「これが円です」と声高に叫ぶ演劇に疑問を感じていたわたしには、『14歳の国』がその疑問に応えてくれたように思われたのだった。戯曲の体裁は同じでも、そこで表現されるものやその方法は実にさまざまなのだなと。
さらに。当時わたしは『14歳の国』のことばの扱い方について注目しあれこれ考えていたのだけれど、読み返してみるともう一つのことにも無自覚に魅かれていたのだと思う。それはこの作品の強い虚構性だ。この作品は中学校の教室で行われた持ち物検査を写実的に描写したものではない。今のわたしにとってはこの点こそが重要なのだけれど、それについて述べるのはまた別の機会があれば、そのときに譲りたい。
とにかくわたしにとって『14歳の国』は表題にあるように「忘れられない」だけでなく、まだ手放すこともできない一冊だということが改めて読み返して分かった。いまだに刺激に満ちていることに正直驚いてしまうが、もう少しいろいろ考えてみたい。
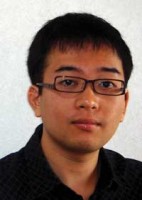
【著者略歴】
田辺剛(たなべ・つよし)
劇作家、演出家。劇場「アトリエ劇研」ディレクター。1975年生まれ。福岡県福岡市出身。現在は京都市に在住し「下鴨車窓」というユニットを中心に創作活動を続けている。
2005年に『その赤い点は血だ』で第11回劇作家協会新人戯曲賞を受賞。2006年秋より文化庁新進芸術家海外留学制度で韓国・ソウル市に一年間滞在し、劇作家として研修する。2007年に『旅行者』で第14回OMS戯曲賞佳作を受賞する。
「忘れられない1冊、伝えたい1冊 第6回」への4件のフィードバック