◎ハイラム・ビンガムがマチュ・ピチュを発見する話(タイトル/作者/出版社不明)
杉山至
秋口だったと思う。私が小学生だった35年くらい前の。
小学校の2階の外れ、木漏れ日の入ってくる放課後の図書室でその一冊に出会った。
インカ帝国? 南米ペルー? マチュ・ピチュ? 当時はまだ、名前も聞いた事のない単語が並んでいて、これが架空の冒険譚なのか実話なのかさえ知らず夢中で文字を追いかけたのを覚えている。
主人公は、実在の考古学者で冒険家のハイラム・ビンガム。彼がマチュ・ピチュを発見するまでの道のりを描いたものだったと記憶している。
内容も面白かったと思うのだが、この本を読んでいるときに夢の中でも白昼でもビンガムと一緒にジャングルを歩き、現地人に遭遇し、見たこともない遺跡と出会うことを妄想し、読書なのに手に汗を握る体験をしたのが忘れられない。
当時の本なので、ビジュアルソースは少なく、言葉で語られる空間のイメージを想像しながら読んだのを憶えている。だからなのか、この本のことを思い出すとストーリーよりも、自分が勝手に妄想した情景として、身体の感覚としてのイメージがよみがえってくる。
1970年代後半、高度経済成長期。私の育った東京の近郊都市の掘り返され変貌していく風景とこの一冊の幻想的な世界が奇妙に重なっている。彼がインディ・ジョーンズのモデルになり、マチュ・ピチュの遺跡が世界遺産になり、有名な観光地になるだいぶ前のことだ。
後に舞台の空間や美術の仕事にも繋がる、冒険や廃墟や失われたものへの興味の入り口に、この本との出会いがあったのは間違いない。
なぜならあの木漏れ日の時から四半世紀後。文化庁の芸術家在外研修員として1年間イタリア・ナポリに滞在したときも、南イタリアから地中海にまたがり多く残る古代の劇場遺構やパフォーミングアートの痕跡を肌で感じてみたいと思ったからだ。
文化の源流を探って脚を伸ばしたギリシャでは、不思議な経験をした。エピダウロスの古代ギリシャ劇場の遺跡を見に行ったときのことだ。たまたまレストランで向かいに座ったアメリカ人と話をしていると、彼は医者だという。医者がなぜ劇場の遺跡を見に来たのだろうか? 興味をもったので、なぜ此処に来たのかと尋ねてみた。すると彼はこの地は、医神アスクレピオスの神殿があった所だという。医者の神殿と劇場? どういう組み合わせ?
後に解ったのだが古代ギリシャでは観劇することはある種の医療行為でもあった。また、神殿と劇場が対になって存在していることも。パフォーミングアートが儀礼や祭儀の一つとして、人々が環境の中に存する超越的なものとコミュニケーションするために必要な行為であったのだということを、ギリシャでのアメリカ人の医者との出会いから始めて身をもって感じたのだった。人間にとってのアート行為の原初の一つがそこにあったのだ。
ハイラム・ビンガムには到底及ばないし遺跡を発見したわけでもないが、私にとってこの出来事は重大な発見だった。日常生活では絶対出会わなさそうな、アメリカ人の医者と日本の舞台美術家がギリシャの古代劇場で出会う。遺跡という大地に書かれた歴史の断片を身をもって体感することが現代の私たちに与えてくれるインスピレーションの深さは計り知れない。
そういえば、あのレストランも地中海のまぶしい陽射しを受けたオリーブの木々からの木漏れ日が奇麗だった。料理はなにを食べたか忘れてしまったけど。
さてこの本、タイトルを思い出せない。なんせ35年も前の12歳くらいのこと。
小学生が読んだ本なので児童書だったと思うのだが、ネットで調べてみてもなかなかそれだという本がない。ただ、主人公の名前ハイラム・ビンガムと言う言葉の響きを、風の中に聞こえる呪文のように、今でもたまにワクワクとした気持ちとともに憶いだす。
【筆者略歴】
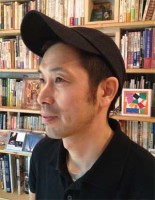 杉山至(すぎやま・いたる)
杉山至(すぎやま・いたる)
1966年東京生まれ。国際基督教大学卒。同大学在学中より青年団に参加。06年カイロ国際実験演劇祭参加作品:地点『るつぼ』にてベスト・セノグラフィー賞受賞。近年は青年団、ポかリン記憶舎、地点、サンプル、東京タンバリン、てがみ座、風琴工房、ダンスシアターLUDENSや、2012年の日生オペラ『フィガロの結婚』等の舞台美術を担当。また舞台美術(セノグラフィー)ワークショップを多数実施。桜美林大学・四国学院大学非常勤講師、NPO法人S.A.I.理事、二級建築士。