◎多層的深みを孕むふり幅
高橋宏幸(近畿大学国際人文科学研究所研究員)
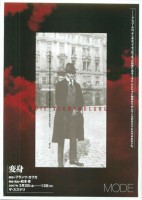 作品がそれのみによって完結されないこととして、たとえばプロセスの重視は、美術ならばプロセスアートやコンセプチュアルアートの一端を占める作品などで知られている。その方法を演劇にあてはめるならば、たとえばリーディングやワーク・イン・プログレスなどを経て、それが公演されるまでの軌跡を公開した作品を指すことになるのだろうか。
作品がそれのみによって完結されないこととして、たとえばプロセスの重視は、美術ならばプロセスアートやコンセプチュアルアートの一端を占める作品などで知られている。その方法を演劇にあてはめるならば、たとえばリーディングやワーク・イン・プログレスなどを経て、それが公演されるまでの軌跡を公開した作品を指すことになるのだろうか。
むろん、それを一つの様式の対象として扱うことは違うだろう。それでは単なる公開前の作品の途中経過を見せただけに過ぎない。重要なのは、その作品が作られる過程を公開することによって中途の反応を伺うことや、劇作家や演出家の足跡をただ見せるだけではなく、その変容が完成されたと思われた作品に対しても、絶えず完結を拒み、変化を見せるように作用することにある。つまり、作品の変化が起こるような偶然性を、あらかじめ組み込むことが方法としてあることを重視するべきなのである。そこではじめて作品の軌跡が問題とされる。
もちろん、演劇の場合ならば、それをジャンルがもつ本来の固有性に還そうとした時期があったことも事実である。60年代末から70年代にかけてアングラと呼ばれた演劇の表象がもった思考の一つには、戯曲から離れて再現ではない現前としての「いま、ここ」という一過性が声高に叫ばれた。いわば、演劇の本来の姿としての偶然性が、その度に舞台を変えていく根幹に据えられたのである。
しかし、その演劇の本質的なものへの傾斜は、三島由紀夫の死という一度きりのパフォーマンスの衝撃と比べればもろくも崩れ去る。
だから、その問題を引き受けるには、やはりそれを方法的に突き詰めることが必要となる。演劇の純粋性という言葉にあぐらをかくことなしに、一過性を絶えず構築しようとする必要がでてくるのだ。
その意味で俳優の訓練方法として最もオーソドックスなエチュードを練り上げて一つ一つのシーンを構成していくことによって、稽古場から公演に至るまで、基本的に戯曲をもとに舞台を作らないMODEの松本修の方法は、当時「新劇」と呼ばれた演劇のメインストリームである文学座にいながら、それこそ一昨年や昨年の唐十郎作品の上演からも分かるように、「いま、ここ」にこだわり続けた「アングラ」の影響の端境に立つものが、自身の方法を作品へと反映させようとしたものだったといえる。
今回の松本修のカフカシリーズの一つに数えられる『変身』も、その方法を踏襲している。カフカの作品のなかでもおそらく一番有名な『変身』は、「ある朝、グレーゴル・ザムザが不安な夢から目を覚ましたところ、ベッドのなかで、自分が途方もない虫に変わっているのに気がついた。」(注1)という冒頭の台詞に示されるように、物語の原因や結果を重視するよりも、虫になったグレーゴルとその家族、女中や間借りしている人々との関係が時にヒューモアとして、時に悲哀や哀愁が滲み出て、その関係の歪な構造が様々な視点から描かれた多層的な作品として知られている。
そして、小説を原作として映画や舞台として実際に視覚に映して作品化させようとするとき、最も注目されるのは、やはりその「虫」をどのように演じるのかということだろう。
今回の演出では、虫をそのまま俳優が人間の姿で演じている。何らかの予備知識を持たない観客がいたとしても台詞と役者が三人連なって虫を演じる場面がワンシーンだけあることによって、その虫がいかにグロテスクなものかという部分が作られる。しかし、そのほとんどは、一人の俳優がそのままの姿で演じている。『変身』の虫を俳優がそのまま上演すること自体は何も特異なことではない。未見だがロシアの演出家であるワレーリイ・フォーキンが演出したカフカの『変身』(注2)もある。だが、その効果は、日本というその場所で演じられる地域性とでもいうべき特色を見せている。
虫となったグレーゴルは、そのまま自分の部屋で妹に世話をされて生活を続けるのだが、それは虫を甲斐甲斐しく世話する妹と母と父の微妙な関係の変化を起こしていく。小説で描かれていることと同じなのだが、下北沢のスズナリという場で見ていると、これはまるで「引きこもり」の状態を思い浮かばせる。引きこもった兄をおびえながら心配する母と怒る父、そして世話をする妹としていつしか見られるのである。
もちろん、それを匂わせるような装置や状況は作られていない。舞台は、前面に主人公のクレーゴルの部屋が突き出ているような形であり、奥に家族が夕食などをとる居間がある。その間を透けた幕が進行に合わせて降ろされたりすることによって、部屋や居間へ観客の視線を集める。そして、カフカの世界の背景に常に見え隠れするプラハの街のイメージを壁の窓から髣髴とさせ、洒落た配置の舞台装置となっている。台詞など作品の進行は、松本修の演出の特徴ともいえるのだが、あくまで原作をなぞるように忠実に作られているのである。
そして原作と同様に、世話をすることに疲れ果てた妹の心が徐々に兄から離れていき、家族は自分たちの生活を維持することに懸命になっていく。生活のために住まわせることになった下宿人たちの前で妹が下手なバイオリンを弾き、彼らがすぐに聞き飽きたのに、それでも弾き続ける姿を見て、怒りのあまり部屋から出て来た虫=グレーゴルを父が追い返すさまは、それこそ現在を騒がすニュースである部屋の一室に閉じ込める監禁事件にも見えてくる。これもまたあくまで原作に忠実に描く様子が、そのような身近なイメージを抱かせるのである。
このように原作におけるカフカの楕円的な作品性、読むたびに様々な視点から読み込める作品性を、松本修の演出の方法によって今回の『変身』は上手く活かしたといえる。
もちろん、この卑近なイメージを巡っては、意図されずとも日本の小劇場を代表するシモキタザワという共同体の世界にカフカの世界を変えてしまったということもできるだろう。たとえば、谷岡健彦はMODEのチェーホフ作品に対して、他者性の欠如によってその作品が完遂されていることを批判している(注3)。その批判は、確かに作品を穿っている。しかし、このカフカ作品への忠実さのために生まれる様々なイメージは、それだけと言い切れない部分もある。
それは、戯曲と身体との対峙が、「新劇」と「アングラ」にとっての他者性であったならば、その端境期に立つ松本修の方法論として選択されたものが、その他者としての俳優のエチュードや演技における偶然性を構成して、作品に入れ込もうとすることだったのではないかということである。演出家が作品を構成して統括する立場にいるならば、制御しきれない部分を持たせればいい。むろん、その偶然性に左右されるということは作品のイメージにもふり幅がでる。だから、その特徴としての洗練された舞台というものが、時に小洒落た舞台にとどまることも起こりうる。
その問題を解消しようとする軌跡が、題材としてアングラという偶然性と、新劇もしくは戯曲という完成された作品を丁寧に読むことによる作品の多層的な深みを孕ませようというふり幅になっているのではないか。少なくとも演出家における方法というものを、松本修はもった演出家であるとはいえる。
(初出:週刊「マガジン・ワンダーランド」第42号、2007年5月16日発行。購読は登録ページから)
(注1)『カフカ小説全集4』 池内紀訳 白水社 2001年
(注2)「舞台上のカフカの世界―ワレーリイ・フォーキン演出『変身』論―」 上田洋子 早稲田大学文学研究科紀要 2001 及び 「カフカ『変身』の演劇的受肉」 上田洋子 『演劇人』 演劇人会議 2002年
(注3)「コドモはわかってやらない」 谷岡健彦 『舞台芸術01』 月曜社 2002年
【筆者紹介】
高橋宏幸(たかはし・ひろゆき)
1978年岐阜県生まれ。演劇批評。近・現代演劇研究。近畿大学国際人文科学研究所研究員。『図書新聞』『シアターアーツ』などで演劇批評を連載。
【上演記録】
MODE「変身」
下北沢 ザ・スズナリ(2007年3月2日-13日)
http://www.honda-geki.com/suzunari/koen/mode.html
原作:フランツ・カフカ
構成・演出:松本修
出演:
小嶋尚樹
高田恵篤
中田春介
榎本純朗
加納健詞
斎藤圭祐
栗須慎一朗
石井ひとみ
山田美佳
美術:伊藤雅子
照明:大野道乃
音響:岩野直人(ステージオフィス)
舞台監督:青木規雄、松下清水+鴉屋
宣伝美術:大久保篤
企画・制作:MODE
チケット料金:一般(指定席)3500円、学生割引2500円