◎「ロック微分法」(渋谷陽一著 ロッキング・オン)
永山智行
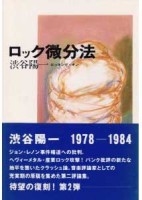
音楽が思考のスタート地点になっている気がする。
劇団で「水をめぐる」というシリーズの作品をつくった時に、俳優の発語の様式として、「生活言語イントネーション」なるものを試してみた。これは、語彙としては共通語のそれを使用するのであるが、その発語においては、俳優個々の普段のイントネーションを採用するというものだ。別に、郷土の言葉を大切にしたい、などという思いではなく、話し言葉の音楽性について考えてみたかったのだ。
わたしたちの劇団のある宮崎県都城市は、アクセント辞典を開くと「アクセント崩壊地帯」と書いてある。それがどういうことなのかはわからないが、確かに、いわゆる共通語のイントネーションとは違う、主として語尾があがるようなイントネーションで言葉を発している。共通語で「こんにちは」と話しかけられても体はそれほど反応しないが、語尾があがるイントネーションで「こんにちは」と話しかけられると、思わず体がふわっとなり、微笑みがこぼれてしまう感覚になる。文字にするとまったく同じ5文字が、そのイントネーション次第で、こうも体を動かしてしまう、そのことに興味があったのだ。
音楽、である。音楽の音楽性は、言葉の意味性を軽々しく凌駕する。現代詩のような、よく分からない歌詞でも、いや、まったくわからない言語であろうが、それがひとたび音楽にのって歌われると、どこまでも体を動かすものとなる。じゃあ言葉なんかいらないんじゃないかと思うが、しかし音楽の音楽性を強く揺り動かしているのはその言葉であることも間違いない。音楽と、言葉と、その関係性。そこにはどこまでも深い、人間が人間であることの源流が流れているのではないか、というのがわたしのこの30年の考えてきたことのような気がする。つまり、人はなぜ歌うのか、と…。
1978年頃から、小学生のわたしはFMラジオをよく聴くようになっていた。もちろん当時の宮崎に民放などないので、聴くのはNHK-FM、お気に入りは平日夜10時からの「サウンド・ストリート」だった。坂本龍一、佐野元春、甲斐よしひろなどのミュージシャンにまじって、正体のわからないDJがひとりいて、それが渋谷陽一だった。そこでかかる音楽の魅力とともに、それを語る渋谷陽一の言葉に惹かれ、やがて渋谷陽一が編集する雑誌「ロッキング・オン」をほぼ毎号のように読み漁った。
この「ロック微分法」はその「ロッキング・オン」などでの原稿をまとめたものであるが、当時ロックの、例えばアルバム1枚をきちんと批評的な言葉で語る、などということがほとんどなかった時代、渋谷陽一や「ロッキング・オン」の、言葉で音楽をとらえようとするその姿勢は新鮮で、その姿勢そのものに、わたしはロックを感じていた。
あれから30年。いまだにわたしは、音楽と、言葉と、その関係性と、に悩み、思考し、体を動かし、失望し、けれどやはりそこに喜びを感じ、そんな風に作品をつくり続けている。そのわたしの思考の原点はここに、この本の中にあるような気がするのだ。
【筆者略歴】
永山智行(ながやま・ともゆき)
1967年生れ。劇作家、演出家。1990年、劇団こふく劇場を結成。宮崎県内の二つの町(門川町・三股町)の文化会館のフランチャイズカンパニーとして活動する一方、2007年からは障害者も一俳優として参加する作品づくり(みやざき◎まあるい劇場)をはじめ、質の高さ、活動の社会的な広がり、その両面から高く評価されている。2006年10月から、宮崎県立芸術劇場演劇ディレクター。
