◎消化されるのを拒む他者性という困難
中村昇司(編集者)
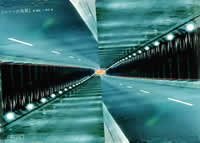 観劇を終えて最初の感慨は、めんどうな作品を観てしまった、というものであった。
観劇を終えて最初の感慨は、めんどうな作品を観てしまった、というものであった。
それはこの作品が、容易に理解・消化されることを拒む異物として、記憶にどっかり居座り続けるであろうものだからだ。人を、考えること、という不安定な世界へ誘うもの、そんな記憶として未消化のまま生きる、そういう作品だろう。
若い夫婦、武と理恵は、武の老いた母・佐代子を老人介護施設にあずけて共働きをし、いずれは沖縄への移住を計画している。その施設から、フィリピン人ハーフでもと男娼であった介護士によって佐代子がベッドごと誘拐され、武や刑事がその行方を追う。
とりあえず、そのようなあらすじが用意されてはいるが、観ていてすぐわかるとおり、そこには、追跡劇にあるべき熱狂や使命感は抹消されている。武は沖縄移住のために仕事を優先し、理恵が気にするのは同じく行方不明になった飼い猫の行方で、刑事は関係者の女性たちを物色するばかりである。また、逃げる介護士もとくに理由も目的ももたず、佐代子の横たわるベッドを牽きながらぐるぐる徘徊するのみだ。途中、武がたまたま、ベッドを牽く介護士と出会ってしまうが、会わなかったことにしましょう、ということにさえなってしまう。
「カロリーの消費」、そこにあえて理由を探すとすればそうとしかいいようのない話。チラシにもそう書かれているとおりだ。
そして、かように「目的」的でない物語であればこそ到達できる視界に、本作は達しようとしているように思う。
作品の物語が「目的」的でないこと、到達すべき結末を持たないこと、それは人物造型とも相同の関係になっている。
劇中でもいわれているとおり、登場人物はいわゆる変態ばかりだ。中でももっとも輝かしいのは介護施設の院長役で、劇中後半ではほぼビキニパンツ一枚で筋肉美を見せ付けながら、同じく全裸に近い介護士とのホモセクシュアルな絡み(倒立エスケープなどのプロレス的ムーブを混ぜる)や四つん這いでのベッド牽きなど、およそ写実性とは遠そうなデフォルメが施された人物像にみえる。それは猫殺しの青年や、ヴァイオリンの下手な奥様の描写ともども、ある種コミカルな類型性を感じさせるものだ。
作中でこの類型性に反抗しようとするのは、歌を探す女・チャコだ。自分の固有性、掛け替えのない唯一の存在としての自分を探している彼女は、まさに「目的」的な追求を行なっている人物といえる。その行為自体がうんざりするほど類型的なものであるのはいうまでもないが。




ここでいわゆる、リアリズムというものを考えておく。管見の限り、それはある特殊性・固有性を詳細に描き出し、それによってある種の普遍性、観客の経験的な共感なり世界の状況なりをも描こうとするもの、と理解している。観客の受けるリアルという感覚はそういった装置の働きといえようか。
その意味では本作の、固有性を欠いたキャラクター、到達すべき独自の内面というものを想定されない、いわばサンプルとして用意された人物群は、どれほど詳細に描写されたところで「リアルな感じ」を与えることに到達するのは難しいはずである。しかし、それでもこのキャラクターたちが、我々の日常における、困った隣人たちを想起させずにおかないとしたら、それは、むしろ我々の内面の類型性、あるいは、我々が他者をある程度類型でしか認識しえていない面のあることを示すだろう。
人物の固有性に関しては、「歌」というものでも描かれる。自分のアイデンティティそのものであるような歌を探すチャコを措いて、劇中では固有性を遺棄した歌が幾度か歌われる。その歌詞はデザートのレシピであったり、なんでもないメモであったり、とるにたらないはずのものだが、これが劇中では賞賛され、実際に聴いていて面白い。理恵の絶望的に下手なヴァイオリンが鳴らすノイズが、バッハの「G線上のアリア」のメロディであることに気付かされる瞬間の衝撃と笑いも同種のものであろう。また院長が即興で歌う「佐代子の歌」は、同年代の女性であれば多く当てはまるはずの時勢や、息子への愛を歌う、いくらでも人名を代入可能で固有性を茶化すようなものだが、それにもかかわらずこの歌は一定の真実味を持ってしまう。
チャコは、この交換可能性が許せない。劇中で行方不明の猫は、青年に殺されているのだが、飼い主である理恵は既に捜索はやめて、新しい猫を飼うつもりでいる。何の理由もなく殺されて、飼い主からも忘れられようとしている猫を、チャコはせめて食べることで意味を与え、掛け替えのなかった存在たらしめようとする。
これは、劇中でも語られている、胎内回帰、母性というものと結びつくかと思う。アイデンティティを保証するものとして、世界に唯一という絶対的なものではなく、ある強い関係性において(たとえば母子という関係性において)、固有性をもつこと。それをやわらかな救いのようなものとして用意している。換言すれば、固有性というものは、他者との関係性の中で相対的に保証されるものだ、ということになろう。
劇中では、母・佐代子は息子夫婦からもあまり省みられず、ほとんど姥捨て山のような介護施設に追いやられ虐待されているのだが、上記の意味で、もっとも類型的であるはずの母性が、逆に(極めて限定的な関係のうちではあるが)固有のアイデンティティを保証するものとして再認識される。
この作品は、冒頭、チャコの独白、回顧のかたちで始まり、終盤、ふたたび彼女の独白が再現されて終幕に向かう構成である。ラストシーン、彼女は自分の歌を歌うことが出来ず、かわりにありふれたスタンダードナンバー、その一人称・ニ人称が自由に交換・代入可能な歌、「ユー・アー・マイ・サンシャイン」を口ずさみ、登場人物全員が舞台に上がっての合奏となる。拙いヴァイオリンやギターが鳴らされ、半裸の男たちが動物のように鳴いたり、四つん這いで歩きまわったり。
最後に彼女の発見する「歌」とは、この小さな世間のくだらない日常、「カロリーの消費」にすぎない日常そのものである。自分だけの固有の歌がどこかにあるはず、という神話めいた強迫観念が夢見たものに比べたら、ずっと醜悪で退屈で、どこにも辿り着かないまま続くものであろう。だが、そんなどうしようもなさを丸ごと全肯定しようとする精神が、ここにはある。
日常、ふとした、くだらないことで笑ったり悲しんだり、それが私であり、それでよいのだ。と、たとえばそのようなものであろうか。
目的、理由のある物語、そして物語的な人物認識は、線状的なわかりやすさと引き換えに、多くの取りこぼしを生むことはよくいわれている。理由の明確でない物語、固有性の表出しない人物が選択された理由は、そのような物語的な線状化を排除したところにリアリティを構築する意図があったように思える。それは虚構作品に対するアプローチとしては、単純な写実描写を追求するスタンスよりも舞台上の虚構性を高める一方で、観客に対してはより強い喚起力を及ぼすものであったろう。
そして、これほどインパクトのある作品にもかかわらず、意味がよくわからないこと、どのように消化し、どういった文脈で理解すればよいのかわからないように作られていること、これも非物語的であればこそだと思う。笑いも下品さも、コントのように消費されるでもなく、また見世物小屋的な露骨さとも一線を画している、絶妙の匙加減だ。
観劇後、めんどうな作品だ、と思ったのも、この消化しにくさ、どのような文脈でもたやすく消化されるのを拒むようなもの、つまり作品内容と逆説的ではあるが、作品の固有性というべきものが強かったからであろう。理解されやすいということは、既存の文脈で処理しやすいということ、芸術としての脆弱さをも示しているのだから、わからなくていいのだ。それだけ強かに、観たものの記憶に生き、考えることに駆り立てるだろうから。
考えること、関係性を構築すること。
この作品に強いて目的のようなものを想定するとしたら、それだろうと思う。
固有性、母子関係に匹敵する他者との関係性を、構築したいとしたらどうしたらよいか? ここで描かれたように、性交して殺して食えばよい? まさか。そんな神話じみたコミュニケーションを模倣しても仕方あるまい。この作品に登場する「変態」たちだって、もっとましなアプローチを考えていたはず。
自分で考えること、それを続けるしかないのだ、そう語っているように思える。
消化しづらいもの、つまり他者性とは、そういうものだ。
まったくめんどうな話だと思う。だが、この困難さは何らかの希望を感じさせるものである気はするのだ。
最後に、末筆になるが、役者の質も大変高く思えたことに触れたい。彼らが演じていなければ、筆者には悪趣味な笑劇としか受け取れなかったかもしれない。また文中では絶望的に下手だと書いたが、おそらく理恵役の役者自身はヴァイオリンが下手ではないだろう。
そして、舞台美術、照明も面白かった。舞台の広い空間に置かれた横長の壁、扉、階段、天上から吊り下げられた可動式の窓枠。この作品の独特の虚構感は、これがあってこそであったと思う。
(初出:週刊マガジン・ワンダーランド第63号、2007年10月10日発行。改題して掲載。購読は登録ページから)
【筆者略歴】
中村昇司(なかむら・しょうじ)
1974年、神奈川県生まれ。音楽誌記者を経て、現在、至文堂編集部にておもに美術誌編集を担当。2006年ごろより趣味で観劇を開始。演劇関係の刊行物に『現代演劇』(今村忠純編 2006)がある。
・wonderland寄稿一覧:http://www.wonderlands.jp/archives/category/na/nakamura-shoji/
【上演記録】
サンプル「カロリーの消費」- MITAKA“NEXT”Selection 8th 参加
三鷹市芸術文化センター星のホール(2007年9月14日-24日)
作・演出: 松井周
出演:
辻 美奈子
古舘 寛治
古屋 隆太
大竹 直
渡辺 香奈
山崎 ルキノ( チェルフィッチュ)
米村 亮太朗(ポツドール)
山中 隆次郎(スロウライダー)
羽場 睦子
舞台美術:杉山至+鴉屋
照明:西本彩
音響:野村政之
衣裳:小松陽佳留(une chrysantheme)
舞台監督:小林智
宣伝美術:京
宣伝写真:momoko japan
記録写真:青木司
記録映像:深田晃司
WEB運営:牧内彰
制作補佐:有田真代(背番号零)
制作:三好佐智子
チケット:前売り 一般2500円 当日 一般2800円 高校生以下 前売り、当日とも1000円
ポストパフォーマンストーク:
ゲスト:14(金) 岩井秀人(ハイバイ主宰、
16(日)佐々木敦(評論家)
20(木) 松田正隆(劇作家・演出家)
21(金) 山下敦弘(映画監督)
【関連情報】
・松井周インタビュー(『映画芸術』NO.420, 2007年夏号)
・サンプル日記(サンプル主宰松井周さんのブログ)