◎政治と劇場の間 ミュージアムで公開された3つの劇作品をめぐる時評的断章
柳沢望
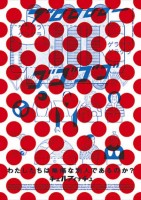
『私たちは無傷な別人であるのか?』の公演を横浜美術館に見に行ったのは3月8日で、これはブレヒト的と言って良い舞台なのだろうな、と見ながら考えた。少なくとも、観客に問いを投げかける上演だった点でそう言えると思う。
ただ、その問いかけのなされ方についてはいろいろ考えてみる余地はあるだろう。それこそ、十分に思考を貫いた上での問いなのかどこかで思考停止した問いに過ぎないのかによって、問いかけの意味も違ってくる。そこに立ち返って考えたいのだけど、その上でこの記事では、中野成樹+フランケンズと、そしてNadegata Instant Party(ナデガタインスタントパーティー)の近作についても言及していく。
さて、ブレヒトのことを思い出したのには理由がある。『エクス・ポ』誌の第二期0号に載った宮沢章夫との対談で岡田利規はブレヒトへの関心を示していたのだった。岡田さんは日本では左翼的な教条主義だったとか頭でっかちだといったイメージがブレヒトにつきまとうことに触れながら「日本でブレヒトが、受容の仕方に誤解があったことの結果としてあんまり取り込まれなかったんだとしたら、それはもったいないですよね」(p.412)と言っていた。
『私たちは無傷な別人であるのか?』(以下『無傷』と略す)の上演をめぐっては、ことさらブレヒトについての言及はなされていないが、潜在的な仕方においてではあれ、この上演でもブレヒトへの関心につながるものはいろいろあったのではないだろうか。
 それで、ブレヒトの名前を出せば中野成樹+フランケンズが上演した『スピードの中身』のことを想起せずにはいられない。僕は3月20日に所沢空港発祥記念館で上演されたものを見に行った。これは、ブレヒトの『折り合うことについてのバーデンでの教育劇』を原作に、石神夏希が誤意訳(フランケンズではそう呼ぶ一種の翻案)をした上演台本に基づいたものだった。
それで、ブレヒトの名前を出せば中野成樹+フランケンズが上演した『スピードの中身』のことを想起せずにはいられない。僕は3月20日に所沢空港発祥記念館で上演されたものを見に行った。これは、ブレヒトの『折り合うことについてのバーデンでの教育劇』を原作に、石神夏希が誤意訳(フランケンズではそう呼ぶ一種の翻案)をした上演台本に基づいたものだった。
『無傷』では、日本社会で進行しつつあると見なされ、そのような感じ方が一般化している、いわゆる「二極化」というか「格差社会」の問題、富裕層と貧困層の落差や分断がモチーフにされていて、それはマンションの一室の情景などを素描するように富裕層の若い夫婦が過ごす日常を切り取った舞台作品だった。
一方、『スピードの中身』は、仕事の現場を描く作品だ。太平洋横断を試みた飛行士の事故をモチーフに、飛行士を救うべきかという問題をめぐって、経営者側と現場で働く人々が会議を行う。
そこで、経営する側に立つだけの能力を発揮する人々と、管理される立場に回る人々が、多少の誇張を伴いながら対比される。その仕方には、格差社会という問題意識が反映されていたようだ。
どちらの作品もその上演において、格差社会について何か答えを出すわけではないが、観客に問いを突きつけ、それぞれの態度を反省するよう促す面を持っていた。そういうところに、単に社会派的に時事問題を取り上げるのとは違う仕方での政治的な側面がうかがえるし、それをブレヒト的だと言っても良いと思う。
中野成樹は、彼なりにブレヒトへの関心を持続させてきた演出家だったし(注1)、岡田利規と中野成樹は、STスポットの同期生とも言えるような近い関係にあって交流も深い。ブレヒトへの関心においても、一脈通じる所があるのかもしれない。
ブレヒトと言えば、近々、フレドリック・ジェイムソンのブレヒト論も本として出版される予定だそうだが、二周目のブレヒト受容が日本でこれから始まるのかもしれない。戦後的な左翼史を相対化した上で、再開発を待つ更地からブレヒトを読み直す、そんな試みのための条件が熟しつつあるというような位置付けをこの二人の演劇作家に与えることもできるだろう。とはいえ、岡田利規と中野成樹の二人の作品に見られる政治性を、単にブレヒトからの影響であると考えなくても良いし、それらの上演をブレヒトに対する忠実さによって評価しなくても良いだろう。
格差社会の問題は、この二人の作品に限らず、近頃の演劇でよく取り上げられている(注2)。そこには、単に社会問題として話題になることが多いからというにとどまらない理由があるのだと思う。つまり、演劇を行うこと続けることそのものが根本的に関連する政治的な問いが、格差社会という図式において前景化され、誰も無視できないものとなっているということだろう。
そもそも、多くの観客を集めるところから始まる演劇は、人々をどのように集めるのか、どのような人々が集まるのかという点において、政治と切り離せないものだが、今の社会は演劇をもっと切迫した政治的な問いの前に立たせている。たとえば演劇への公的な助成をめぐって国や自治体の予算をいかに配分すべきかを問うことは、芸術に限らないあらゆる分野からそれぞれ切実に公的な予算を求める声があがっているなかで、演劇の取り分をいかに主張するかという問題であり、それ自体政治的であるほかない問いだ。そして、演劇の創り手であろうとする人の多くが、高い収入を見込めない状況にある。大まかに言って、演劇の作り手は所得の再分配をめぐって、社会における芸術的な価値と自分たちの生存という、いわば上部と下部の二つの側から政治的な問いにはさみうちにされている。状況がそうだとして、この二人の演出家は、格差社会という政治的モチーフに対して、どのような政治的な身振りを示したと言えるだろうか。
『無傷』では、ある種の昔話のように類型化された簡潔な叙述の文体を重ねながら、何をしているわけでもない休息時間の意識のあり方を軸にして、私的な視点から路上の光景や室内の情景など労働と労働の合間の場面を切り取っていて、そこで幸福とその経済的な基盤のあり方についての問いが繰り返される。 いままでチェルフィッチュを特徴付けていた若者がしゃべるような冗長な語りやだらしなく動き続ける身体性といったスタイルとは一線を画した、より彫琢されたセリフと演技の新しいスタイルが示された。上演のディテールについての細かな描写は他のレビューや記録類に譲ることにして、幸福についての問い、そして不幸を体現するような人物の登場について注意を向けたい。

『無傷』では、ひと組の若い夫婦の生活が作品の中心に据えられていて、そもそもこの作品は、若い夫が「幸せな男」だと断定的に形容されることから始まる。高い収入が得られる仕事があって、人生のパートナーも居て、これから豪華なマンションに引っ越そうとしている。そういう物質的に満ち足りていることが幸福だと断定されるというようにこの舞台の語りは進んでいって、幸福ってそもそも何なのだろうか?物質的に満たされれば幸福なのか?といった問いは、作品の中では宙吊りにされている。だからこそ、その問いが観客に強く意識されるという風でもあった。
その問いが極まるのは、妻の描写においてだったろう。若い妻は自分が経済的に私生活において何の不自由もないという幸せな状況にあることには何の根拠もないと漠然としたしかし深い不安を抱いているように描写されていてそうした理由のはっきりしない不安に陥って涙を流している気持ちをでも夫は理解しようとしないしそこに問題があるとも思っておらず表面的な感情の揺れはただ宥めておけば良いと考えているというかそこは何も考えていない人物であるみたいに夫は描かれていた。
そういうところがセキュリティが確保されたマンションに住んでいる「無傷」な存在として若い夫婦を描いているということかも知れない。そんな妻が夫の帰りをひとり部屋で待っているところに安定した職業も生活も奪われていて不幸を体現するような不穏な男が訪れるという場面が中盤に描かれる。山縣太一が演じたその男はドアのベルを鳴らしてインターフォン越しに若い妻に対して語りかけ富を奪われたものが富を得ているものに対して持っている恨みをぶつけるように自分が不幸であることがいかに不当であるか不正義であるかを粘着的に問い詰めていくし物質的な幸福に甘んじている者にはそういうまるで理不尽なクレーマーみたいな問いかけに耳を傾ける責任があるみたいに言い立てる。
山縣太一が演じる、まるで非正規雇用によって将来を奪われたワーキングプアの代表というか、プレカリアートを露悪的に戯画化したような若い男の言葉を聞いていて、僕はあまりに図式的でリアリティを欠いた描写だなと感じないではいられなかったのだけど、劇の進行上、その場面がまるごと、劇中の世界において実際には無かったことだと語られることになる。そのリアリティの無さは、そのまま劇中の世界では、なかったこととして非現実なもの、リアルでないものに配分されてしまっているわけだ。それはまるで自分の幸福自体が新自由主義的な社会の中で偶然配分された立場に過ぎず、いつ自分が持たないものに転落するかわからないいくらでも置き換え可能なものに過ぎないと感じている妻が不安を人物像に投影した妄想であるかのように解釈できる、そんな風に処理されてしまう。
そこから考えられるのは、逆に、不幸を体現した不在の男と劇中世界に実存させられる幸せな夫婦との比例関係が、類比的に、作品が描く舞台表象の全体と僕たちの具体的な生活そのものとの関係に近いのではないかと思われてくるということだ。
山縣太一が描き出す不幸な男が図式的過ぎて現実感を欠いているように、若い夫婦の物質的幸福とそれに伴うと示唆される精神的な不幸さというものもまた、図式的過ぎて現実感に乏しい。そして、現実にはそんな夫婦は居ないしそんな事実は無かったというに過ぎないとも言える。実際朝日新聞の記事で岡田利規は次のように取材に応じている。
つまり、わりと細かく描写される若い夫婦のイメージもまた、リアリティに欠けた舞台表象によって塗りつぶすことで想像したり共感したりできない他者をその背後に示すようなものだった。こんなことは実際には無かったし、こんな図式的な人物は居ない、という自覚が、その背後の現実を感じさせるというような。つまり、他者性を上書きして舞台から消し去ることによって逆説的に他者性を示すような作法が、現実世界の表象環境において他者性が排除されることの裏返しの強調になっている、そういった風な意図そのものが、この作品の演技とセリフの文体を要請していたのではないだろうか。そういう意味では、この若い夫婦を中心として描かれる舞台表象の全体が『三月の5日間』に出てくる、犬に見えるホームレスの姿と同じなのかもしれない。この作品での舞台表象の全てはまるで、ホームレスを犬として描いてしまっているようなものなのではないか。
つまりここでは、幸福と不幸にまつわる問いそのものが、現実には及ばない問いとしてしか示されていない。これが単に中途で手放された問いでないとするならば、幸福や不幸についての問い、つまり、正義についての問いは結局そのようなものでしかありえないのではないか、という、問いそのもの本質的な不全さを問うという構造をここに読み取ることができる。
観客としては、正義についての問いは本質的に不全であらざるをえないのではないかという問いに麻痺してしまうこともできるし、あるいはそこから、ともかく無作法な問いかけは慎むべきだと考えることもできる。正義について単純に割り切れないと感じることこそが正義への道を踏み外さない作法であるというように。
ここで、このような作品の身振りが、演者たちの舞台上での身振りとどのように関わりあうのかについて問い続けるべきだろうが、その問いはこの作品の再演やこれから読まれるだろう戯曲に向けて開いたままにしておきたい。いずれにせよ、ここにこそ政治的な難問が示されていると言えるだろう。
この上演で舞台に掲げられたリアルタイムを示す時計や、キッチンタイマーなどで繰り返し強調される時間間隔は、劇中の時間と舞台上の時間が決して一致しないことを幾度も明示している点において、舞台表象が、描こうとする現実に届かないことをむしろ強調していたのだろうか。
他方『スピードの中身』は、架空の航空会社で行われる会議という形で、ブレヒトの原作を「誤意訳」していて、大西洋横断に失敗し死亡したパイロットが死に切れずに、自分は救助されるべきだと会議の場で訴えるというような、すこしファンタジックな物語をメタフィクション的に描く舞台作品になっていた。場面としてはまるで企業の会議室で現場スタッフと経営側ないしプロデューサー側が議論のテーブルに着いていて、経営/プロデューサー側に現場がまるめこまれてしまうという風な描写が、軽妙な喜劇的タッチで描かれていく感じだ。その範囲で多少誇張されてはいるけれど、演技の質はナチュラルな感触を保った再現的なものだったといえる。上演台本がブレヒトの原作をどのように改変し加工したかについて、そして演技や演出の手法がブレヒト的な方法論に対してどのような位置を持つものかについても慎重に問うべきだろうが、それは専門家による検討にゆだねたい。

この舞台作品は、二部構成をとっている。前半では、技術が発展しても貧困は解消されないというような統計資料が討論の材料として示されたりもして、技術の進歩が人類にもたらすものは何か、そのための個々人の犠牲についてどう考えるべきか、といった大きな問いが矢継ぎ早に提示されていく。より高く飛びたいという飛行士の無垢で個人的な意欲は、公的にはどのような価値を持つのか、それは国や社会が守るべきものなのかどうか、といったすぐには答えられないような問いが次々に示されていくのだが、「勝ち組」的でいかにも有能そうな女性マネージャー風の人物や大物プロデューサー的で食えないオヤジ風の人物が、まるで事業仕分けの会場ででもあるかのように、うじうじとした現場の逡巡をあっさりと片付け、暴力的に回答を与えてしまう。そういう筋立てがしかし、個人のささやかなこだわりややりがいといったものを効率的に処分してしまって良いものだろうかという問いと、しかしそれもまた世界にあふれる悲惨や貧困を前にして贅沢すぎる要求なのではないかという問いとの板ばさみになるような図式を示していて、これはそのまま、演劇に対して切迫している問いでもあり、どちらかといえば身近な存在として描かれる飛行士や整備士たちは、そのまま演じている役者たち本人の姿であるようにも見えてくる仕掛けになっていた。
ところが後半でその物語は飛行士が恋人を整備士にとられてしまうという話にすりかえられ飛行士の死も失恋に置き換えられて、会議の場では、前半で技術革新に関連して示されていた飛行機事故の統計が女性の恋愛遍歴(いままでの彼氏の数)に置換され、技術の進歩が女性が恋の手だれになっていくということに転換されて、会議の議題も飛行士は恋愛をあきらめるべきかどうか、という話に変わってしまう。そんななんだか卑近な恋話によってすっかりパロディにされてしまって、人類の歴史や文明や正義やといった前半の大きな問いがすっかり肩透かしをくらってしまうという格好だ。
この構造は、正義についての問いをめぐって、今度は僕たちが不全であるのではないかと問いかけているようだ。前半の問いは大きすぎる問いをきちんと受け止めることができずに即断しなければならないという困難を示しているようだし、後半の問いは卑近過ぎる問いにしかし振り回されざるをえないという困難を示しているようだ。そして、人生のパートナーをどう選ぶかという問いも、貧困や社会問題と個人の尊厳とをどう考えるのかという問いも、それぞれに固有の大切さを割り振られるべきことだろうけど、大きな社会問題については深刻ぶって考えこんでしまい、恋の話は下らないと思いこんでしまう、そんな荘重さと卑近さみたいな対立図式そのものが錯覚のようなもので、いかに僕たちが問題を適切に捉えられないかということを問題の脱臼において問いかけてくるようでもあった。
観客はその脱臼に呆然として思考停止してしまうこともできるし、脱臼状態を脱臼のまま耐えることにこそ難問があると考えることもできる。いずれにせよ、そこにこそ政治的な難問が示されていると言えるだろう。
この舞台で背後に掲げられていた短針のない、長針だけの時計が示す脱臼した時間は、まさにそのように問題が脱臼し続ける位相を示していたのだろうか。
さて、ロラン・バルトはブレヒトの劇作品について、歴史に苦しみながら歴史に盲目である人間が舞台に描かれるのを見ることで、観客が歴史への責任を自覚する、そういうものだと解説していた(バルト著作集4巻、みすず書房pp.5-6)。チェルフィッチュ『無傷』では、歴史に対して盲目であることを自覚させられているのは観客自身だったかもしれない。あるいは『スピードの中身』では、歴史への責任に対して適切な距離が取れないことをこそ観客は自覚させられたのかもしれない。ともかく、どちらの作品においても舞台で示されていたのは、政治的な問いの切迫をなんとかやり過ごす身振りにおいて問いの困難さを示すことだったと要約できるだろう。
しかしそれは、演劇がちょっとしたやり直しの機会を与えられている今だけに許された、過渡的な猶予においてのみ可能なことなのかもしれない。そうした問いの切迫へのつかのまの猶予というイメージもまた、今の社会状況が課してくる枠組みの中でつきまとう偏見に過ぎないかもしれず、日本のあり方が変わるにつれて、今のような演劇の状況は遠からず消え去るのかもしれない。
 いずれにせよこの点で示唆的なのはNadegata Instant Party (ナデガタと略す)のワークショップ企画「一日で野外市民劇をつくる“Closing Museum, Opening Party”」で上演された、即席で仕上げられた市民劇『とじて、ひらいて、その手を上に』という作品のあり方だ(注4)。
いずれにせよこの点で示唆的なのはNadegata Instant Party (ナデガタと略す)のワークショップ企画「一日で野外市民劇をつくる“Closing Museum, Opening Party”」で上演された、即席で仕上げられた市民劇『とじて、ひらいて、その手を上に』という作品のあり方だ(注4)。
ナデガタは、参加型のアートイベントを展開してきた現代美術系のユニットで、成果としての作品よりも作品を口実に関わりを生み出すことを主眼において活動してきた。今回の市民劇も、演劇としてのクオリティよりも、上演に一般市民の参加者や観客を巻き込んでその場で生まれる活動が示す関係性のあり方こそアートとして提示されたのだと解釈すべきなのだろう。
演劇としては、わりと良くある小劇場系の雰囲気もあるような飛躍の多い物語で、スリルとサスペンスあふれる風ないかにも芝居じみた展開をする。出演者は台本を片手に素人芝居をするに過ぎない。お芝居の設定は、練馬区の美術館が国際企業に買収され改装のためにバリケード封鎖されるというお話だが、その寓話的な図式において、高尚な芸術を一部の教養ある観衆向けに提示するようなアートのあり方と、地元の市民も参加しながらお祭り的にイベントを行うようなアートのあり方とが対比されて行き、最後には「美術館開放」を叫ぶデモ隊が美術館の中に乱入するのだが、無料で見に来た観客たちもいつのまにかエンディングでデモ隊のエキストラを演じさせられてしまうというものだった。
宮下公園のナイキパーク化とそれに対する抵抗運動といった最新の時事ネタも織り交ぜながら、政治活動のパロディに観客を巻き込んでしまう仕掛けはどこか軽妙なシニカルさを持ちながらも、巧みに、アートと政治をめぐる絡み合った問いのだたなかに観客をまるごと投げ込んでしまう。
この事例から考えられるのは、単純に言って、政治的な問いを演劇的に提示するためには上演の質は高くなくても良いということだ。むしろ、上演の質を高めるために観客をおとなしく客席に着かせておくことが、上演の政治性を制限するかもしれない。ブレヒト率いるベルリナーアンサンブルがパリで上演した『肝っ玉おっ母』を見たロラン・バルトは、「ブレヒトの作品には、演劇の歓びがある」と評価し(著作集2巻p.93)、「ブレヒトの演出は実はたいへんな豊かさを要求する」(同p.222)と述べていたが、最後にはブレヒトの演劇は「繊細さと美的資質のゆえに、政治的には決して有効なものとはなりえなかった」と結論付けるに至った(『明るい部屋』みすず書房、p.51)。
ここに取り上げるような類の現代演劇は、もっぱら富裕な人々が嗜むようなものでもなく、かといってポピュラーな商業的コンテンツでもないようなものとならざるを得ない。そうした条件において「より高い質」を求めることは、作家の単なる欲望、あるいは鑑賞者の単なる欲望の反映に過ぎないかもしれない。その欲望は尊重されるべきものであり、そうした欲望が公然と満たされることは社会的に良いことであるのだとしても、それは公的な資金で支援すべきことではなかったかもしれない。そのような問いの切迫に耐えることは演劇においてしばらく課題であり続けるだろう。いずれにせよ上演の質を求めること自体の政治性は幾重にも問い返されざるをえない。
『無傷』も『スピードの中身』も、そしてナデガタの市民劇も、奇しくもミュージアム(美術館/博物館)で上演された。この符合は、劇場という場所そのもののあり方を問い返すという現在的な要請の現われだったのかもしれない。そんな劇場という施設に対する問いかけは、しばらくの間、他の演劇作家たちにも反映せずにはいないだろう。その問いが演劇に突きつけられることが幸福なことなのかどうか、有効なことかどうかは、まだわからないが、ともかく、つかのまのものかもしれないこの猶予において、上演芸術そのものにつきまとう曖昧さや不純さの意義を最大限噛み締めておきたい。
(初出:週刊マガジン・ワンダーランド第186号、2010年4月14日発行[まぐまぐ!, melma!]。購読は登録ページから)
注1:次のインタビュー参照。(「根っこはないけど大切にしたいものはある-「誤意訳版」翻訳劇の源 ワンダーランド2006年2月01日掲載)http://www.wonderlands.jp/interview/004nakano/
ブレヒト作品の「誤意訳」上演も何度か試みられている。
注2:最近では『F』が二極化をモチーフにしていた。次のレビューを参照。(柳沢望「閉ざされた世界の底にわずかに残る演劇の希望」)http://www.wonderlands.jp/archives/12605/
注3:出典 http://www.asahi.com/showbiz/stage/theater/TKY201001290311.html
注5:練馬区による記録 http://www.city.nerima.tokyo.jp/manabu/bunka/museum/kyouikuhukyu/houkoku/nadegata.html
関連ブログ記事http://nadegata.exblog.jp/13039583/
【筆者略歴】
柳沢望(やなぎさわ・のぞみ)
1972年生まれ長野県出身。法政大学大学院博士課程(哲学)単位取得退学。個人ブログ「白鳥のめがね」。
・ワンダーランド寄稿一覧:http://www.wonderlands.jp/archives/category/ya/yanagisawa-nozomi/
【上演記録】
1.チェルフィッチュ「わたしたちは無傷な別人であるのか?」
STスポット(2010年2月14日-26日)
横浜美術館レクチャーホール(2010年3月1日-10日)
作・演出:岡田利規
出演:山縣太一 松村翔子 安藤真理 青柳いづみ 武田力 矢沢誠 佐々木幸子
前売3,000円/学生2,500円/当日3,500円(整理番号付き自由席)
2.中野成樹+フランケンズ『スピードの中身』
三渓園旧燈明寺本堂(2010年3月13日-14日)
所沢航空発祥記念館(2010年3月20日-21日)
演出:中野成樹
誤意訳:石神夏希(ペピン結構設計)
ドラマトゥルク:熊谷保宏
美術:細川浩伸(急な坂アトリエ)
音楽:石川智子
技術監督:佐藤泰紀
制作:加藤弓奈
キャスト フランケンズ:村上聡一、福田毅、洪雄大、竹田英司、田中佑弥、
石橋志保、斎藤淳子
ゲスト:小泉真希、北川麗
前売・当日2,500円(全席自由・税込)
別途、入園料・入館料500円が必要。
3.Nadegata Instant Party プロデュース野外市民劇公演『とじて、ひらいて、その手を上に』
練馬区立美術館 正門階段 及び 野外広場(2010年3月21日)
【出演】「ワークショップ/一日で野外市民劇をつくる。」参加者
【脚本・演出】Nadegata Instant Party
【音響】 ポイ野、AGAGA
【スタッフ】“Closing Museum,Opening Party” CREW
【宣伝美術】中西要介
【イラスト】井上コトリ
【料金】無料(予約不要・全席自由)
【主催】練馬区立美術館